歴史上で看取されることのうちで戦争のなかで起こったことほど重要だったり強大だったりする事績はないということは明らかであろう――真理に関する判断に基礎を置きたいと望むとすれば、の話だが。なんとなれば我々がよく知っている他の戦争の中でよりもそれら〔プロコピウスが語るユスティニアヌス時代の戦争〕の中でいっそう注目に値する偉業が成し遂げられてきたからである。なるほど、この話の読者が古代に栄光の座を与えて現代の事績は注目に値するものに勘定する価値がないと考えたとしてもそうなのである。例えば、今日の兵を「弓兵」と呼ぶ一方で、最も古い時代の兵を「接近戦の戦士」、「盾兵」といういとも高尚な語やこういった類いのその他の語で呼ぶのを好む人たちがいる。そして彼らはその時代の勇敢さはまったく現代まで残ってはいないと考えているが、これは実に不用心で完全にこの主題〔戦争〕の実際の経験から乖離した意見である。持ち前の技術から引き出されたこの語で不運にもあざ笑われているホメロスの中の弓兵に関して言えば、彼らは馬で運ばれるわけでもなく槍や盾によって守られているわけでもないということにこの人たちはまったく考えが及んでいない。事実、彼らの体を守る物は一切なかった。彼らは徒歩で戦いに突入し、仲間の盾を〔防備として〕選んだり堡塁の上で、その後ろで安全を確保するための墓石を探したりすることで自らを隠すことを強いられており、こういった状況のおかげで彼らは敗走の憂き目に遭ったり素早く移動する敵に襲いかかった際には身の安全を確保できなかった。彼らは開けた場所での決戦に加わることは到底なかったが、常に戦いの参加者の物を盗もうとしていたらしい。これとは別に彼らは弓の使用に無関心なあまり獣にしか弓の弦を引かなかったほどで、そのために放たれた飛び道具は当然のことながら物の数ではなく、命中した人には無害だった。過去の弓術がこういったものであったことは明らかである。しかし現代の弓兵は胴鎧を着込んで膝まで伸びた脛当てを装備して戦いに向かう。右側に矢を、もう一方の側に剣をぶら下げている。槍を自分に結びつけて装備し、肩に取手のない小型盾の一種をつけて顔と首の部位を覆う者もいた。彼らは熟練した騎兵であり、全速で駆けている時に造作なくどちらの側にでも弓を構え、追撃の時も敗走の時も敵を射ることができた。彼らは弓の弦を額に沿って反対の右耳へと引き、進路上に立つ者は誰であれ殺せるほどの力で矢を放ち、盾と胴鎧などはこの威力には歯が立たなかった。そこでもまだこういった事柄のどれも考慮せずに古代を尊敬し崇敬し、現代の改良に信を置かない人たちがいる。しかしそういった考慮によって最も偉大で見事な偉業がこれらの戦争〔ユスティニアヌス時代の戦争〕で成し遂げられたという結論を下すのが妨げられることはあるまい。その歴史は、ローマ人とメディア人の戦争での運命、彼らの逆転と成功とについて述べる幾分か隔たった時代のことから辿ることから始めるつもりである。 テオドシウスが成年に達して人生の盛りに至ってイスディゲルデスが病で世を去ると、ペルシア王バララネス〔ヤズデギルド一世の子バハラーム五世〕が強力な軍隊を連れてローマ領へと攻め込んだ。しかし彼は被害を与えられず何も成し遂げることなく帰国した。以上のことは以下のようにして起こった。オリエンス道担当将軍アナトリウスはテオドシウス帝によってペルシア人への使節としてお供をつけず一人で送られていた。メディア軍に接近すると、ひとりぼっちの彼は馬から飛び降りてバララネスのところへと徒歩で進んだ。彼を見ると、バララネスは近くにいた人たちにやってくるこの男は何者かと尋ねた。この人はローマの将軍だと彼らは答えた。そこで王はこれほどに度を超した尊重で言葉を失うほど驚き、自ら馬を廻らして去り、全ペルシア軍が彼に続いた。自領にたどり着くと、彼は大変真心を込めて使節を接見し、アナトリウスが彼に求めた条件での停戦協定を承認した。しかし彼は一つだけ条件を付け加えた。それは両者いずれも新しい要塞を自領内のうち両国の国境線に近い場所に建設しない、というものであった。この協定が施行されると、両君主はそれぞれの国の事柄を最善と思うように統括し続けた。 このエフタルに向けて進軍したペロゼスは、たまたまゼノ帝によって彼の宮廷に送られていたエウセビウスという名の使者を同行していた。さてエフタルは攻撃に完全に怯えて逃げているように敵に見せかけ、四方を険しい山々で閉ざされていて広大な木々の鬱蒼とした森で守られた地点へと大急ぎで退却した。この時、木々の間から長い距離を進んでくると広々としたどこまでも続くように伸びた道が谷の中に現れるが、ついに至るところにはまったく出口がなく、山に囲まれたまっただ中がその終点となる。かくして完全に油断して考えなしになっていたペロゼスは自分が敵地を進軍していることを忘れて無警戒に追撃を続けた。フン族の一つの小部隊が彼の前方を逃げていた一方で、彼らの軍の大部分は凸凹した地形に身を隠したことで敵軍の後ろを取った。しかしそれでも彼らは、敵が十分罠に踏み込んでできる限り山の間まで行ってもはや引き返せなくなるようにするために敵に姿を見られまいとした。メディア軍が全てこの通りになると――彼らは危機のちらつきに気づき始めていた――ペロゼスを恐れて自分たちの状況について話すのをやめていたにもかかわらず、王を以下のように説得してくれるようエウセビウスに熱心に懇願した。すなわち、自らの窮地に全く気付いていない王が自ら際だった大胆さを見せつけるよりはむしろ相談をして自分たちの身の安全を確保する方途を検討する方が良い、と。かくして彼はペロゼスの面前へと赴いたが、面前の破滅について全く示すことができなかった。代わりに彼は寓話を始めた。曰く、ある時、獅子がそれほど高くはない山の上で縛られて泣き言を言っている山羊に出会った。そしてその獅子はその山羊をご馳走にしようとし、その山羊をひっ捕らえようと飛びかかったところ、非常に深い壕に落ちてしまった。そこは出口のない堂々巡りの狭く終わりのない道の先にあっただけであるが、それもそのはず山羊の持ち主たちがまさにこの目的のためにこしらえて獅子への餌として山羊をその上に乗せたというわけだ。ペロゼスはこれを聞くと、おそらくメディア軍は敵を追撃することで墓穴を掘っているのではないかという恐怖に襲われた。したがって彼はこれ以上の進撃をやめたが、いる場所にとどまって善後策の検討を始めた。この時までにフン族はもう身を隠すことなく彼に追っており、敵が最早後退できない場所の入り口までおびき寄せていた。ついにペルシア軍は自分たちの苦境がどんなものであるかを知るに至り、状況は絶望的だと感じた。というのも彼らはこの危機から絶対に逃がれられる希望はないと感じていたからだ。そこでエフタルの王は何人かの部下をペロゼスのもとへと送り、このおかげでペロゼスが自らとペルシアの人々を理不尽に破滅させたところの彼の無思慮さと無鉄砲さを長々と叱責したが、たとえそうであってもペロゼスがあたかもご主人様であることを証明するかのように王の前に平伏するのに甘んじ、ペルシア人の間での伝統的な宣誓でもう二度とエフタルの国に刃向かわないと誓約するならばフン族は彼らの解放を認めるつもりだと告げた。ペロゼスはこれを聞くと、臨席していたマゴス僧たちに相談し、自分は敵に押しつけられた条件を飲むべきかどうか尋ねた。マゴス僧たちが答えて言うに、宣誓に関して彼は好きなように事を決めた方が良いが、残りのことについては策略をもってして敵を出し抜くべきであると。そして彼らは、日ごとに昇る太陽に平伏するのはペルシア人の習わしであり、したがって彼は時をきっちり見計らって夜明けにとエフタルの指導者と会い、昇る太陽に向き直って敬礼をするべきだと彼に思い起こさせた。こうやって彼らは、彼が行動の不名誉を将来にわたって逃れることができるはずだと説明した。したがってペロゼスは和平についての宣誓を行い、マゴス僧の提案そのままに敵にぬかずき、こうして全メディア軍を連れて無傷で喜びつつ母国へと退却した。 ペルシア人が語るこの真珠の話は、ひょっとしたらいくらかの人たちには全く信じられないようなものとは見えないであろうから、語るに値するものである。それというのも彼らは、その真珠はペルシア湾を洗う海の牡蠣の中にあり、その牡蠣は海岸からそう遠くないところを泳いでいたと言っている。その二枚貝の両方が開けば真珠がその間に鎮座し、その見事な見かけときたら大きさといい美しさといい、歴史上のどの真珠もまったく歯が立たないほど立派なものであった。非常に大きくおそろしく獰猛な一頭のサメがこの見かけを愛し、朝な夕な近くで見守っていた。食料のことを考えざるをえなくなると、このサメは自分がいる所だけで食べられるものを探し、小物を見かけるとさっと襲って急いで食べた。それからこの牡蠣に追いつくと、サメは愛する光景に再び満足した。彼らが言うには、ついにこれが泳ぎ行くのに一人の漁師が気付いたが、怪物への恐怖から危険に尻込みした。しかし彼は事の一切合切をペロゼス王に報告した。さてペロゼスは彼の説明を聞くと、彼らが言うには、その真珠に強い憧れを抱いてこの漁師をたくさんのお世辞と褒美への希望で説得した。君主のしつこさに根負けした彼はペロゼスに以下のように言ったといわれる。「陛下、人間にとって大事なものはお金であり、もっと大事なのは命でありますが、全ての人にとって一番価値があるのは我が子でございます。もとより子供たちへの愛に強いられれば人間は何であれ敢然と行うものでございましょう。さて、私はその怪物を試してみて、陛下を真珠の主にしたいものと思っております。そしてもし私がこの戦いを制したならば、今後私がめでたい人間と勘定される人たちの列に入るということは明らかでございましょう。というのも諸王の王たる陛下が私に全ての良き文物を褒美として与えるであろうことは相応しからぬことではないからですし、私としては、自分が褒美を貰えないでいるとしても、自分が主君の恩人であることを見せつけるだけで十分満足することでしょう。しかしもし私がこの怪物の犠牲になる必要があるとすれば、なるほど、陛下、王のすべきことは父の死について私の子供たちに報いることでございましょう。そうすれば死後にさえ私は――私が自分にとって最も近しい人たちの稼ぎ手になればそれだけあなた様が善行で勝ち得る大きな名声は大きくなることでしょう――我が子たちを助ける報酬となり、あなた様は自分に恩のことで感謝する力を持たない私に恩恵を施すことになりましょう。それというのも気前の良さは死者に示される時にのみ不純物のないものになると見なされているからです」こう言って彼は出発した。そして牡蠣がいつも泳ぎ、サメがその後をついてきている地点に来ると、彼は岩の上に座って崇拝者がいなくってひとりになった真珠を取る機会をうかがった。サメが食べられる物をたまたま見つけて牡蠣から遅れてしまうや否や、漁師は浜にこの任務のために自分に付き従っていた人たちを残し、牡蠣めがけて真っ直ぐに突き進んだ。彼がすでに牡蠣を取って大急ぎで海から出ようとしていたところ、サメが彼に気付いて救出のために突っ込んできた。漁師はサメが来るのを見て、浜までそう遠からぬところで追いつかれそうになると戦利品を全力で陸へと投げ、自らは間もなく捕捉されて破滅の憂き目に遭った。しかし浜に残された人たちは真珠を拾い上げて王のもとへと持っていき、一切合切を報告した。私が書き留めた限りではペルシア人がこの真珠について語る話は以上のようなものである。このあたりで元の話に戻ることにしよう。 こうしてペロゼスは全ペルシア軍共々滅ぼされた〔484年。〕。たまたま壕に落ちなかった僅かな兵たちは敵の慈悲に自らを委ねることになった。この経験の結果、敵地を進軍している間は敵が力負けして潰走していようとも追撃を行ってはならないという一つの法がペルシア人のうちに作られた。かくしてペロゼスと一緒に進軍していなかった者と自国に残った者はペロゼスの末子で唯一の生き残りだったカバデスを王に選んだ。その時、ペルシア人はエフタルに服従して年貢を払うようになり、これはカバデスが勢力をこの上なく確固たるものとして最早彼らに年貢を払う必要がないと思うようになるまで続いた。この蛮族がペルシア人を支配した期間は二年間に及んだ。 かつてペルシア人とアルメニア人との間で二、三〇年に及んだ休戦を挟まない戦争があり、この時はパクリウス〔シャープール二世〕がペルシア人の王で、アルメニア人の王はアルサケス家のアルサケス〔二世〕だった。長く続いた戦争のために双方は限界を超えた被害を被り、とりわけそれはアルメニア人に顕著だった。しかし両国は他方から非常に距離が隔たっていたため、交戦国に和平を打診できないでいた。その時、ペルシア人が、アルメニア人とそう遠くないところで暮らしていた他のある夷狄との戦争に取り組む運びとなった。したがってアルメニア人はペルシア人に好意を示して和平を求めるようとやっきになってその夷狄の土地に攻め込むことを決定し、手始めにペルシア人にその計画を披露した。それから彼らはその夷狄に不意打ちを仕掛けて老いも若きもそのほとんど全ての者を殺した。そこでその好意をいたく喜んだパクリウスは最も信頼する友人たちをアルサケスのもとへと送り、身の安全の保障を宣誓して自分の面前へと招待した。アルサケスが彼のもとへとやってくると、パクリウスはありとあらゆる親切を示し、兄弟として共に並んで歩くほど厚遇した。そこでパクリウスは、ペルシア人とアルメニア人は以後は本当に互いを友人にして同盟者とすることとし、最も厳粛な誓約で彼を縛って自らも同様の誓約を行った。その後、彼はすぐにアルサケスを解放して自分の国へと帰した。 これからそう遠からぬうちにとある人たちが、何らかの扇動的な計画を実行しようと企んでいると言ってアルサケスを中傷した。パクリウスはこの人たちに説き伏せられ、全般的な事案を相談したいと伝えて再び彼を召喚した。何の躊躇もなく王のもとへと来たアルサケスはアルメニア人のうちで最も好戦的な者たちを同行させており、その中にはその時の王の将軍であり相談役だったバッシキウスがいた。それは彼が知勇を目覚ましいほどに兼ね備えた人物だったからだ。そこでパクリウスは、アルサケスとバッシキウスが宣誓された協定を反故にして舌の根も乾かぬうちに騒擾を企むようになったとして両者に非難を雨あられと浴びせた。しかし彼らは嫌疑を否定し、そういったことを自分たちは企んでいないとこの上なくしつこく誓った。したがって当初パクリウスは彼らを監視下に置くことでその顔に泥を塗ったが、後になってマゴス僧たちに彼らをどうすれば良いかと尋ねた。さて、そのマゴス僧たちは罪を否認していて明らかな罪状が見つからないこの者たちに有罪判決を下すのは決して公正ではないと考えたが、嫌が応にもアルサケスその人が自らの告発者になってしまうような一計を王に提案した。彼らは彼に王用の天幕の床に半分はペルシアの土を、もう半分はアルメニアの土を敷き詰めさせた。王は指示の通りにこれを行った。それからマゴス僧たちは魔術の儀式をして天幕中で呪文を唱えた後、王にアルサケスを伴ってそこを歩きつつ宣誓された合意への違反を非難するように仕向けた。さらにマゴス僧たちは自分たちが会談の場にいて然るべきであり、こうすれば皆が発言の証人となるはずだと言った。したがってパクリウスはすぐにアルサケスを召喚し、マゴス僧たちが隣席する天幕で彼を連れて行ったり来たり歩き始めた。パクリウスはこの男になぜ宣誓した約束を反故にしてペルシア人とアルメニア人を重大な厄介事でさらに困らせようとするのかと問うた。さて話し合いがペルシアの地から取られた土で覆われた地面にさしかかってもアルサケスは否定し続け、自分はパクリウスの忠実な臣下であると主張するというこの上なくぞっとするような誓いをした。しかし喋っている最中に彼が天幕の中央にさしかかってアルメニアの土地に足を踏み入れると、何らかの未知の力に強いられて突如として挑戦的な口調に変わり、自分が主人になればすぐにこの無礼に対してパクリウスとペルシア人に復讐をするつもりだと公言し、パクリウスとペルシア人を脅すのをやめなくなった。引き返してペルシアの土の地面に戻ってくるまで彼は歩いている間中に若者らしく愚劣な言葉遣いで話し続けた。そうかと思えば取り消しの詩〔パリノディア(palinodia)。古代ギリシア以来のヨーロッパで作られた、直前に言ったことを撤回するための詩。有名どころでは、プラトンの『パイドロス』の中でソクラテスが議論の中でついエロス神を悪し様に言ってしまったことに対し、罪を清める取り消しの詩としてエロスを称揚する話をしている。〕を歌うかのように以前のような調子でパクリウスに哀れっぽい申し開きをする嘆願者になった。しかしアルメニアの土に再び来ると彼は脅迫に転じた。このようにして彼は何度も何度もコロコロ立場を変え、いかなる秘密も秘匿できなくなった。そこでついにマゴス僧たちは協定と誓約を反故にしたとの判決を彼に下した。パクリウスはバッシキウスの皮を剥いでその皮で鞄を作り、もみがらを詰めて高い木から吊した。アルサケスはといえば、パクリウスは王家の血筋の人間を殺すつもりはまったくなかったので、忘却の監獄に閉じ込めた。 この後にペルシア人はその夷狄〔アルメニア人〕の国へと進軍し、アルサケスがペルシアの土地に来た時にも随行したアルサケスと特に懇意なとあるアルメニア人を同行させた。この男はパクリウスにも分かるほどこの遠征で自身が優秀な戦士であることを証明し、ペルシアの勝利の立役者となった。このためにパクリウスは何であれ拒まないと保証して彼の望みを叶えさせてくれと頼んだ。このアルメニア人は自分が望むような仕方で一日だけアルサケスに敬意を捧げること以外何も求めなかった。さて、これに王は甚だ苛立ち、かくなる上は非常に古いある一つの法律を無視することを余儀なくされるに違いなかった。しかし自分の言葉を完全なる真実とするために彼は要望が認められることを許した。この男が王の命令によって忘却の監獄を見つけると、彼はアルサケスに挨拶し、両者は互いに抱擁し合って優しい嘆きの声をかけ合って彼らに降りかかった厳しい運命を悲しみ、やっとこさ互いへの抱擁から離れた。それから彼らは泣きながら座ってから涙を止め、件のアルメニア人はアルサケスを入浴させ、何一つおろそかにせずに身なりを完全に整えて王の外套を着せ、イグサの寝台の上に横たわらせた。それからアルサケスはその場にいた人たちを以前の彼の習慣通り王らしい饗宴でもてなした。この宴の間、多くの酒杯の上で演説がなされてアルサケスをいたく喜ばせ、彼の心を喜ばせる多くの出来事が起こった。酒宴は日暮れまで続いて皆が相互の交わりをこの上なく夢中になって喜んだ。ついに彼らは大変嫌々ながらも互いに離れ、幸福をありったけ吹き込まれた形で分かれた。それから生涯の最も甘美な一日を過ごして何よりもないのを寂しがっていた交際を楽しんだ後には最早人生の悲惨さに喜んで耐えるつもりはないということをアルサケスがどんな風に言ったかを彼ら〔「彼ら」とは言い伝えをしたペルシア人であろうか。〕は述べている。彼が言うには、これらの言葉を言いつつも実のところ宴の際にわざと盗んだ短刀を自らに突き立て、彼らのもとから旅立った。このアルサケスに関する話は以上のようなもので、私が述べた通りのことが『アルメニア史』で物語られており、この折に忘却の監獄についての法律が一時停止された。だが私は脱線した点へと戻るべきだろう。 カバデスはセオセスを伴って捜査の目を完全にかいくぐってエフタル系フン族のもとに到着した。そこで〔エフタルの〕王は彼に娘を娶らせ、今やカバデスが義理の息子になると彼はペルシア人に対する遠征にあたって実に恐るべき軍勢の指揮を任せた。ペルシア人はこの軍と遭遇するのをまったく嫌がって方々へと急いで逃げた。グサナスタデスが権力を行使していた領地へと至ると、カバデスはその日に自分の面前へとやってきて奉仕を申し出た最初のペルシア人をカナランゲスに任命するつもりだと何人かの友人に話した。しかしこう言いはしたものの、ペルシア人の官職は栄誉ある出自の者以外には与えられてはならないと定めたペルシア人の法律を思い浮かべたために彼はこう話したことを後悔する羽目になった。というのも彼は目下のカナランゲスの親族の誰かが最初に来るのではないか、そして自分の言葉を守るために法に無視せざるを得なくなるのではないかと恐れていたからだ。それにしても彼がこの問題を検討するに、偶然が起これば法を無視することなく彼はそのまま自分の言葉を守ることができる。たまたま彼のもとに最初に来たのはグサナスタデスの血縁で特に優れた軍人だったアデルグドゥンバデスという若者だった。彼はカバデスに「陛下」と呼びかけて王としての彼に最初に服従し、どんな任であれ奴隷として自分を使ってくれるよう求めた。それからカバデスは何の問題もなく王宮へと進路を取り、バラセスから擁護者を奪い取り、熱して猛烈に沸騰させたオリーブ油を開いた両目へと注ぎ込む、あるいは鉄針を火で温めて眼球を突き刺すという悪人に対してペルシア人が一般的に使っていた目潰しの方法を用いて彼の両目を潰した。その後バラセスは幽閉されたまま二年間ペルシア人の上に君臨した。グサナスタデスは殺されてアデルグドゥンバデスが彼に変わってカナランゲス職に据えられた一方で、セオセスはすぐに「アドラスタダラン・サラネス」という全官庁と全軍の権限に人を任命できる称号となると宣言された。後にも先にも誰もこの官職を与えられなかったため、セオセスはペルシアでこの官職に就いた最初にして唯一の人物であった。賢明さと活発さでカバデスの右に出る者はいなかったため、王国は彼によって強化されて堅固に守られた。 この時、シリア人の中にヤコブスという名の正義漢がおり、彼は宗教に関わる諸事では非常に厳格な人物だった。よりしっかりと敬虔な瞑想に没頭できるようにとこの男はアミダから一日のところにあるエンディエロンと呼ばれる場所に長年引きこもっていた。この地の人々は彼の目的を支えるために彼の周りを杭が連なりつつも間隔が空いた垣根で囲み、このために近くに来た人は彼を見て話をすることができた。彼らは彼の頭上に雨と雪を防ぐのに十分なほどの小さな覆いをこしらえた。そこでこの男は暑さにも寒さにも耐え、毎日というわけではないが長い間隔を空けて豆を常食にすることで命を繋ぎつつ長らく座っていた。さて、その地方をうろついていたエフタル兵の一部がこのヤコブスを見つけ、彼を射殺しようとして非常に熱心に弓を構えた。しかし彼らの中の誰の手も動かなくなってまったく弓を扱えなくなってしまった。これが軍の間で言いふらされてカバデスの耳に入ると、彼は自分の目でこの様を見てみたいと思った。そしてこれを見ると彼と彼に付き従っていたペルシア人は甚だ仰天し、彼はヤコブスに夷狄どもの罪を許してほしいと懇願した。彼は許しを口にし、この男たちは苦悶から解放された。それからカバデスは多額の金を所望するだろうと思いつつもこの男に何か望みはないかと尋ね、自分は何であれ拒まないと若者らしく無鉄砲に言い添えた。しかし彼はカバデスに戦争の間に彼の捕虜になる者全員を自分に譲渡するよう求めた。この要望をカバデスは飲み、彼の身の安全に関する特許状を与えた。そしてこの行いが広く知れ渡ったために予想通り非常に多くの人が方々から彼のもとへと集い、そこに身の安全を見出した。かくして事の次第は以上のようになった。 アミダ包囲中のカバデスは「羊」〔城壁を叩く部分が羊の頭を模した破城鎚。〕として知られる兵器を防備のあらゆる部署に差し向けたが、町の人々は羊の横向きに木材を投げて絶えずそれらの頭を外した。しかしカバデスは城壁がこの仕方では成功裏に攻撃できないと悟るまで弛まず試し続けた。何度も城壁に打撃を加えたにもかかわらず、彼はどこの防備もてんで壊すことがでず、揺るがすことすらできなかった。まことこの安全は大昔にそれ〔城壁〕を作った建設者の仕事の成果というわけだった。これに失敗すると、カバデスはその都市を脅かすために城壁を遙かに上回る高さの人口の丘を作ったが、籠城軍は防備の内側から丘に伸びる坑道を密かに地中に掘り始め、それは丘の内側の大部分をくり抜くまで続けられた。しかし外部は最初の形のままなので誰も何が起こったのか気付きようがなかった。したがって多くのペルシア兵が安全だと思ってそこに登り、要塞の内側の人々の頭めがけて射撃を行おうと頂上に陣取った。しかし夥しい兵士がそこに一気に群がったために丘は突如崩れ、彼らのほとんどが死んだ。そこでカバデスは状況の挽回の手立てはないと見て取って包囲を解くことを決意し、翌日に軍に撤退命令を出した。それから籠城側は自分たちの危険になど頓着していないとでも言うかのように夷狄を要塞から嘲笑い始めた。これに加えて何人かの娼婦たちが恥知らずにも服をまくって近くに立っていたカバデスに見せつけ、一人の女の体の男には当然ない部分が露わになった。これが明らかにマゴス僧の目に入ると彼らは王の面前に赴き、これはアミダ市民は間もなくカバデスに秘密と隠し立てしているものの一切合切を露わにするということが起こることだという解釈を言い放って撤退を防ごうとした。かくしてペルシア軍はそこに留まることとなった。 何日もせずに一人のペルシア兵が塔から眺めていたところ古い地下道の入り口を目にしたが、それは僅かばかりの小さい石で不用心に隠されていただけだった。その夜、彼は一人でそこに向かってその入り口が円形の城壁の内側に繋がっていることをを検分した。用意した梯子を自ら運びつつ王は僅かな部下を連れて次の夜にそこに来た。そしてこの一欠片の幸運を喜んだ。それというのもその通り道に一番近いところにあった塔の守りは、監視の点では一番用心深い「修道士」と呼ばれていたキリスト教徒たちに割り当てられていたからだ。この人たちはたまたまその日は神ための年ごとの宗教的な祝祭を続けていた。夜が来た時、祝祭のおかげで彼ら全員は非常に疲労していて、いつもの習慣に反して食べ物と飲み物を持って座り込んで甘く優しい眠りに落ち、そのおかげで何が起こったのかに気付けなかった。かくしてペルシア兵は要塞内部への通路を抜けて進んで瞬く間に塔に乗り込み、眠っていた「修道士」たちを一人残らず殺した。これを知るとカバデスはこの塔に近い城壁へと梯子を運んだ。これは白昼堂々と行われた。そして隣接する塔を守り続けていた町の兵たちは厄災に気付き、大急ぎでそちらへと走って救援に赴いた。次いで長い間両軍が他方に雪崩れ込んで戦い、城壁に登ってきた多くの兵を殺して梯子へと投げ落とすなど町の兵が優位に立ち、あと一歩で危機を脱出できそうだった。しかしカバデスは剣を抜いてこれで絶えずペルシア兵を脅しつけ、自ら梯子へと急かして彼らが後に引くのを許さなかった。退こうと身を翻した者を待っていた罰は死刑だった。この結果、ペルシア軍は数を頼んで優位に立ち、戦いで敵を打ちひしいだ。かくしてこの年は包囲が始まってから八日目にして力攻めで落とされた〔503年1月11日。〕。続いて市民に対する大虐殺が起こり、これは年老いた聖職者だった一人の市民が市内に騎乗してやってきたところのカバデスに近づいて捕虜を殺戮するのは王らしからぬ行為だと話すまで続いた。そこでまだ激情に突き動かされていたカバデスはこう答えた。「しからばなぜ貴様らは余に刃向かって戦おうと決めたのだ?」老人はすぐに答えた。「それは我らの決定と同じくらいに陛下の勇気によって神がアミダを陛下の手に授けようとしたからでございます」この話を喜んだカバデスはこれ以上の虐殺を許さなかったが、ペルシア兵に財産を略奪して生き残りを奴隷にするがままにさせ、奴隷の中で全ての貴族を自分のために選び出すよう命じた。 これからすぐに彼はペルシア人ゴロネス指揮下の一〇〇〇人の守備隊、ペルシア人の日ごとの要求に召使いとして仕えることを宿命づけられた僅かばかりの不運なアミダ市民をその地に残してから出発した。彼自身は残りの全軍と捕虜を連れて帰路についた。捕虜たちはカバデスから王たるに相応しい寛大な扱いを受け、その後すぐに全員が解放されて帰国させられたが、力尽くで逃げることは許されなかった。そしてローマ皇帝アナスタシウスも彼らの勇気に相応しい栄誉を示し、その都市に七年間全ての毎年の税を免除すると伝え、彼ら全員を一つの身体を持ちながら多くの良きものを別個に持った各々の人として表現したため、彼らは自分たちに降りかかった不運を完全に忘れてしまった。しかしこれは後年のことである。 さてこの軍は動員がかなり遅れており、進軍もトロトロしたものだった。この結果、ペルシア軍は突如襲いかかっては戦利品を全部持って自国へとすぐに引き上げていたために彼らはローマ領で夷狄軍を捕捉できなかった。アミダに残されていた守備隊が大量の物資の蓄えを運び込んでいたことに気付いてはいたものの、敵地に攻め込むのを躊躇したためにどの将軍も当面は彼らの包囲に取りかかろうとはしなかった。しかし彼らは一緒に夷狄に向けて進軍せず、別々に進んで離れて野営していた。たまたま接近したおかげでこれを知ったカバデスはローマの国境へと大急ぎで向かって彼らに立ち塞がった。しかしローマ軍はカバデスが全軍を率いて自分たちの方へと動いていることをまだ知らず、いるのは小規模なペルシア軍だと当て込んでいた。したがってアレオビンドゥス軍はコンスタンティナ市から二日の距離にあるアルザモンと呼ばれる土地に陣を敷き、パトリキウスとヒュパティウスはアミダ市から三五〇スタディオンも離れていないシフリオスと呼ばれる土地に陣を敷いていた。ケレルはというとまだ到着していなかった。 カバデスが全軍を率いて到来しつつあることを突き止めるとアレオビンドゥスは野営地を放棄して全軍を連れての逃亡に転じ、コンスタンティナへと急いで退却した。そう遠からぬうちにやってきた敵は無人の野営地を鹵獲してそこにあった資金を手に入れた。そこから彼らは速やかに他のローマ軍の方へと向かった。この時パトリキウスとヒュパティウスはペルシア軍の先発隊だったエフタル人部隊八〇〇人と遭遇し、これをほぼ皆殺しにした。次いでカバデスとペルシア軍のことをつゆ知らぬ彼らは自分たちが勝利を得たと思って警戒怠るようになった。いずれにせよすでに日中の〔食事に〕適当な時間が近づきつつあったので彼らは武器を山積みにして昼食の準備をした。さてこの地には小川が流れていて、そこでローマ軍は食事用の肉を洗い始め、また暑さに参っていた一部の兵たちは川に入っており、その結果として小川の流れは濁った。一方カバデスはエフタル兵の身に降りかかったことを知ると敵へと急行し、小川の水がかき乱されていることに気付くと事の次第を見抜き、敵の準備はできていないとの結論に達してすぐに全速で敵に突撃をかけるよう命令を下した。それから彼らはすぐに食事中の無防備な敵に襲いかかった。ローマ軍ははなから踏み止まることができず、抗戦しようという考えをすぐに捨てたが、各々がでできる限りで逃げ始めた。ある者は捕らえられて殺され、他の者はそこに立っていた丘を登って非常に混乱して恐慌状態になりながら岩壁から落ちていった。そして一人もそこから逃げられなかったが、パトリキウスとヒュパティウスは劈頭いの一番に逃げ延びていた。この後、敵のフン族が領地の北部に攻め込んだためにカバデスは全軍を連れて帰国し、この人々と彼は王国の北部で長く続く戦争をした。他方で他のローマ軍もまた到着したが、遠征軍の最高司令官になるような者がおらず、将軍全員が対等の階級だったおかげでいつも意見が対立して一体となることがまったくできなかったために何ら語るに値することを成し遂げなかった。しかしケレルは麾下の部隊を連れてニュンフィウス川〔現代のバトマン川。ティグリス河の支流で、トルコ南東部のバトマン州とディヤルバクル州の境を成す。〕を渡ってアルザネネ〔アルメニア王国南西部〕に侵攻した。この川はマルテュロポリスに非常に近く、アミダからおよそ三〇〇スタディオンのところにある。かくしてケレルの部隊はその地方一帯を略奪して長居せずに帰国し、この遠征全体は短期間のうちに完遂された。 ローマ軍がまだアミダ市の前に野営しておらず、その近辺からかなり離れたところにいた時、鶏とパンとその他多くの食料を持って密かにその都市に入ってはグロネスにこれらを高値で売りさばくのを常としていたある現地人がパトリキウス将軍の前にやってきて、もし報酬を確約してくれるのならばグロネスと二〇〇人のペルシア兵を手中に収めてご覧に入れようと約束した。将軍は彼が望む物は何であれ寄越すと約束してこの男を帰した。それから彼は恐ろしげな仕方で衣服を裂き、嘆き悲しむ人のような外観を呈しつつその都市に入った。そしてグロネスの前に来て髪を振り乱しつつ言った。「旦那、わしはたまたま村から良い品々を全部運んでおったんですが、ローマ兵どもがわしを見つけて――あんたらも知っての通り、彼らは絶えずこの地を小部隊でほっつき歩いて哀れなこの土地の者どもを痛めつけておるんです――辛抱できんほど殴りつけて一切合切を分捕って去って行ったんじゃ。この盗人どもは昔からの慣れでペルシア人を怖がっては農民を痛めつけておるんです。でも旦那、あんたはあんた自身とわしらとペルシア人を守ろうと考えておられる。もしあんたがこの都市のはずれに狩りに行けば滅多にない遊びができましょうぞ。なぜならこの下手人の悪党どもは四、五人で盗みを働きに来るもんですから」彼はこのように述べた。グロネスは説き伏せられ、この男にその試みを実行するのにどれだけ多くのペルシア兵が十分だと考えられるかと尋ねた。彼は以下のように言った。一挙に五人以上と会うことはないから五〇人ほどいればいいが、予期せぬ状況に備えるためには一〇〇人もいれば無事でいられるだろうし、より多くの人数の中の一人の人間に危害が与えられることはないだろうから、もしこの倍の数がいれば全方位を見張れるのでもっと良い、と。したがってグロネスは二〇〇人の騎兵を選抜してこの男に道案内をさせた。しかし彼は、手始めに土地の下調べをするために〔斥候を〕送る方が良く、もし彼が同じ地方でローマ軍がまだうろついているのを見たとの言伝が帰ってくれば、ペルシア軍は適当な時に出撃すべきだとグロネスに主張した。こうして彼はグロネスに良い話をしたと思われたため、彼が彼自身の命令で先遣された。それから彼はパトリキウス将軍の前に出て一切合切を説明した。将軍は彼と共に自らの槍持ち二人〔英訳では単にbody-guardだが、原語ではdoryphorosであり、これは将軍や政治家の私的従者ないし私兵のうち、士官に相当する階級である。〕と一〇〇〇人の兵を送った。彼は彼らをアミダから四〇スタディオンほど離れていて谷と木々の生い茂った土地の真只中にあるティラサモンと呼ばれる村のあたりに隠し、そこで待ち伏せをするよう指示した。それから彼自身は走ってその都市に向かい、グロネスに獲物の準備ができたと話すとグロネスと二〇〇人の騎兵を敵の待ち伏せ地点まで案内した。ローマ軍が待ち構えていた場所に彼らがさしかかると、グロネスにもペルシア兵にも気付かれることなく彼はローマ軍に待ち伏せ地点から声で合図を出して敵を指し示した。そして自分たちに向けて兵が襲いかかってくるのを見ると、ペルシア軍は事があまりにも急だったので仰天し、動揺して何をすればいいか分からなくなった。背後に敵がいたおかげで彼らは後方に退却できず、敵地ではどこにも逃げられなかったからだ。しかし彼らは状況下が許す限りで戦闘隊列を組んで攻撃部隊を撃退しようとした。しかし数が非常に劣勢だったために破れ、グロネスを含む全員が殲滅された。さてグロネスの息子はこれを知ると深く悲しみ、同時に自分が父を守れなかったことに激しい怒りを覚え、グロネスが寝泊まりしていた聖人シメオンの聖域に火を放った。しかし、この建物一軒を除いてグロネスもカバデスも確かに他のペルシア人も、何にせよアミダの他の建物やこの都市の外の建物を取り壊したり破壊したりすることが適当だと見なさなかったことは特筆されるべきである。だが前の話に戻ることにしよう。 それからローマ軍は金を与えることで敵に落とされてから二年ぶりにアミダを取り戻すこととなった。そして彼らは市内に入ると、彼ら自身の怠慢とペルシア人が保持していた間の困難が露わになった。というのもそこに大量の穀物が残されていて、すでに去った大勢の夷狄のことを当て推量していたところ〔敵軍が多ければそれだけ多くの食料があると期待していたということであろうか。〕、グロネスと彼の息子は長い間必要以上に倹約してペルシア軍を食わせていたにもかかわらずおよそ七日間の食料しか市内に残っていなかったのを見て取った。上述のように、ペルシア軍は彼らと一緒に市内に残ったローマ人には敵が包囲を始めた時から何も分配しないことを決めていたからだ。そしてその人たちはまず慣れない食べ物に頼り、あらゆる禁じられたものに手をつけ、ついには互いの血をすすることさえした。こうして将軍たちは夷狄に騙されたことを悟り、兵士たちが自分たちに対する忠誠の欠如を示したことを咎めた。それは大勢のペルシア兵とグロネスの息子を戦争捕虜とすることができて都市そのものをも占領することができた時に彼らが結果として敵にローマの金を渡すことで注目に値する不名誉を自らにもたらしてアミダをペルシア軍から銀で買い取ることになったためであった。この後、ペルシア軍はフン族との戦争が長引いたため、打ち合わせに七年間かけてローマ人ケレルとペルシア人アスペベデスによって作り上げられた協定をローマ人と結んだ。それから両軍は帰国して平和を維持した。したがってすでに述べたような具合で始まったローマ人とペルシア人との戦争はこのような終結を見た。さてここでカスピ門に関わる出来事の話に移ることにしよう。 アナスタシウス帝はカバデスと協定〔506年に終わったアナスタシウス戦争の停戦条約。〕を締結した後、ダラスと呼ばれる土地に際だって強固でまことに重要な都市を建設して皇帝自身の名〔アナスタシオポリス〕を与えた。さて、この地はニシビス市から一〇〇スタディオンに二スタディオンほど欠けるだけの距離があり、ローマ人とペルシア人を分かつ国境線から二八スタディオンのところにあった。そしてペルシア人はその建設を妨害したかったものの、実施中のフン族との戦争に拘束されていたために成し遂げられなかった。しかしこの戦争を終わらせるや否やカバデスはローマ人に手紙を送り、メディア人とローマ人との間で以前交わされた合意で禁じられているにもかかわらずペルシアの国境近くに堅固な都市を建設したことを非難した。したがってその時のアナスタシウス帝は一面では脅迫によって、一面では彼との友情を強調して金を使わずに彼を買収することで騙してその非難を逸らしたいと思った。また、この皇帝によってもう一つの都市が建設されており、このアルメニアの都市は最初の都市と同様にペルサルメニアの国境のすぐ近くにあった。さて、この土地は昔から一つの村があったが、テオドシウス帝の好意によって都市としての栄誉を得て、それどころか彼にちなんだ名〔テオドシオポリス〕を付けられさえした。しかしアナスタシウスはここを非常に堅固な城壁で囲み、こうして他の都市に劣らずそれらの都市からペルシア人に攻勢をかけた。それというのもそれら両方の都市はペルシア人の国にとって脅威となる要塞だったからだ。 この言伝がユスティヌス帝の元に届けられると、彼自身は大喜びし、皇帝の甥で帝国を彼から受け取る予定だったユスティニアヌスも同様だった。そして彼らはローマ人の法が規定する通りに文書でその養子縁組のとりまとめを実行しようと急いだが、その時の皇帝の相談役で財務官の役職に就いており、公正で誰も買収が全くできない人物だったプロクルスに待ったをかけられなければその通りになっていたことだろう。法律を進んで提案したり、物事の定着した順序を乱そうとしたりする意志を持っていなかった彼はこの時にもその提案に反対してこう言った。「新しい計画を実行するのは私の流儀ではなく、他の何よりも新しい計画をまことに恐ろしく思っております。この事柄についてとりわけ大胆な方がいたとしても、その人はこのようなことをすることには気乗りしないでしょうし、そこから起こる波乱に震えおののくものと私には思われます。それといいますのも、目下のところ、尤もらしい口実でペルシア人にローマ帝国を譲り渡すことについての問題を措いて考えるべきことは我々にはないと私は信じるものであります。彼らは隠し立てをしているわけでも隠れ蓑を使っているわけでもないのですが、我々の帝国をこれ以上の騒ぎを起こすことなく我々から奪い取ることを要求するという彼らの目的をはっきりと認めつつ、単純な見かけでその明白な詐術を覆っており、うわべだけの無関心さの背後に恥知らずな目論見を隠しておるのです。その上でお二方は全力で夷狄のこの企みを退けなくてはなりません。おお、皇帝陛下、御身がローマ人の最後の皇帝とならぬように、そして、ああ将軍閣下、ご自身が帝位を得るにあたっての躓きの石であることの証となってはなりませぬように。それといいますのも、見せかけの言葉で隠されるのが常であるような他の諸々の悪巧みは何度も解釈者を必要とすることになるかもしれませぬが、この使節派遣は公然と、そして最初の文言からはっきりと、このホスローが何者であれ、この彼をローマ皇帝の養子縁組に基づく相続人とすることを意味しております。私はこの問題については以下のような理由を閣下に提示いたします。自然的に父祖の所有物は息子のものであり、全ての人の諸法はその多様な自然本性の故に常に互いに対立する一方で、この問題に関してはローマ人と他の全ての夷狄も互いに声を揃えて息子が父の遺産の主人たるべしと宣言しています。もし閣下が選べば、最初の決定を行うことになります。閣下がそうすれば、閣下はその全ての帰結に同意しなければなりません」 プロクルスの言ったことは以上のようなことであった。皇帝とその甥は彼の言葉に耳を傾け、何をすべきかを検討した。その一方でカバデスはもう一通の手紙をユスティヌス帝に送ってきて、その中で自分との和平を樹立するために令名高い人たちを送って文書の形で彼の望みである息子の養子縁組を行う仕方を定めることを要求した。そしてまったく以前にも増してプロクルスはペルシア人の企みを公然と非難し、彼らの関心はローマの勢力を可能な限り確実に自分たちに譲渡させようとすることだと主張した。彼は以下のような意見を提案した。和平が可及的速やかに締結されるべきであり、最も高貴な人たちが皇帝によってこの目的のために送られるべきである。そしてこの人たちはカバデスがホスローの養子縁組を行う仕方を尋ねた時にははっきりと答えなければならず、それがこの夷狄にはお似合いに違いない、と。そしてプロクルスが言わんとしていることは、夷狄は文書によってではなく武器と鎧によって息子を養子にするものだということだった。したがってユスティヌス帝は最も高貴なローマ人らにそう遠からぬうちに彼らの後を追わせてできる限りの仕方で和平とホスローの件について合意を取り付けさせるつもりだと約束して使節団を去らせた。また彼は同じ要旨を書簡でもカバデスに答えることにした。したがってローマ人からは先帝アナスタシウスの甥でオリエンス担当司令官の職責にあったパトリキウスのヒュパティウス、シルウァヌスの息子でパトリキウスのうちで著名で父祖を通してカバデスに知られていたルフィヌスが送られ、ペルシア人からは大権と最高の権威を持ち、アドラスタダラン・サラネスの称号を帯びたセオセスという名の人物、マギステル職にあったメボデスが送られた。これらの人たちはローマ人とペルシア人の領土の境界線上にある地点にやって来てそこで会し、どうやって困難を遠ざけて和平の問題を有効な仕方で解決するかを交渉した。和平の詳細が双方にとってできる限りよく整えられたと見えたならばビュザンティオンへと自ら向かうためにホスローもニシビス市から二日ほどの旅程の距離にあるティグリス川の方へとやって来た。さて双方で彼らの間の困難に関して多くの話がされたが、とりわけセオセスは今ではラジカと呼ばれるコルキスの土地について言及し、そこは昔からペルシア人の属国であってローマ人は力尽くで自分たちからそこを奪い、正当な根拠なく分捕ったのだと述べた。これを聞いたローマ人はラジカすらペルシア人の議論に上がるのかと考えて立腹した。そして彼らはホスローの養子縁組は夷狄にとって当然な通りに執り行われるに違いないと言い返すと、それにペルシア人は我慢ならなかった。したがって双方は分かれて帰国し、その出来事にひどく立腹したホスローは、自らへの侮辱に対するローマ人への復讐を決意しつつ何ら成すことなく父のもとへと去って行った。 この後、主君からそうしろと支持を受けていないにもかかわらずセオセスがラジカの議論を故意に提出して和平を頓挫させ、そしてまた自身の主君をてんで良く思っておらず和平の締結とホスローの養子縁組を邪魔しようとしていたヒュパティウスと以前にも話をしていたと言ってメボデスがカバデスに対してセオセスを中傷し始めた。そして他の多くの告発もまたセオセスの敵たちによって提出され、彼は法廷に召喚された。今や裁判に参加すべく招集されたペルシア全体の代表者は法への尊重よりも嫉妬によって突き動かされた。というのも彼らは自分たちに馴染みのない彼の役職に対して徹頭徹尾敵対的で、その人の生来の気性に敵意を持っていたからだ。というのもセオセスは全く買収できない人物で正義を厳格に尊重する人物だった一方で、他の人とは比べようのない程の横柄さを煩っていたからだ。現にこの資質はペルシアの役人たちには生得的なものであるように思われたが、セオセスの中ではなおのことその弊害がまったく異常な程に増長していたと彼らは考えていた。かくして彼の告発者たちは上記で示された全てのことを述べ、これに加え、この男は決して定着した生き方を喜ばずペルシア人の慣習を守らなかったと言った。のみならず彼は奇妙な神を崇めており、近頃妻が死んだ時にはペルシア人の法律では死者の遺体を地中に埋めることすら禁じられていたにもかかわらず遺体を埋葬した、と。したがって法廷がこの男に死罪を言い渡した一方で、カバデスは一友人としての同情でいたく心を動かされてはいたものの、決してセオセスを助けようとはしなかった。他方で彼は自分が彼に憤慨していることを知らしめることはなかったが、彼が言う限りでは、彼が生きて王になれたという事実は主にセオセスのおかげだったためにセオセスは命の恩人ではあったものの、ペルシア人の法に背くのも気が進まなかった。したがってセオセスは有罪になって人々のもとを去った。彼と共に創始された官職は彼と共に終わった。それは他の誰もアドラスタダラン・サラネスにならなかったためである。ルフィヌスもまたヒュパティウスを皇帝に向かって中傷した。この結果、皇帝は彼を職から解任し、この中傷が全く根拠のないものなのかを探るために彼の仲間の或る者にこの上なく残忍な拷問を加えた。しかしこれ以降は彼がヒュパティウスに害を及ぼすことはなかった。 その後イベリア人はビュザンティオンに姿を現してペトルスが召喚に応じて皇帝のもとにやって来た。それ以降に皇帝は、たとえラズ人が嫌がろうとも自分がラズ人の国土防衛を支援すべきだと要求し、エイレナエウスを指揮官とする軍を送った。この時、ラジカには二つの要塞があり、そのうち一つはイベリア国境からラズ人の国に直接入れるところにあり、これらの要塞の防衛の任務に彼らが非常な難儀していたにもかかわらずこの任務は昔から現地人の任であった。というのも穀物も葡萄酒も他の良い物品もそこでは生産されなかったからだ。現に人力で運ぶというのでない限りは道の狭さの故にそこへはどこからも何も運ぶことができなかった。しかしラズ人はそこで生育するキビの一種で暮らすことができたが、それは彼らがそれに慣れていたからであった。皇帝はその守備隊をその地から外し、ローマ兵はそれらの砦を守るべくそこに配置されるよう命じた。当初、ラズ人はその兵たちのために苦労しながら食料を運んだが、後になって彼らはその仕事を諦めてローマ軍はそれらの砦を放棄したため、ペルシア軍は難なくそこを手中に収めた。ラジカで起こったことは以上のようなことであった。 そしてシッタスとベリサリウス指揮下のローマ軍がペルシア人に服属する地域であるペルサルメニアへと進出し、その地方の広域で略奪を働いて夥しいアルメニア人捕虜を連れて撤退した〔527年。〕。この二人はいずれも最初の髭が生えたばかりの若者で、後におじのユスティヌスと帝国を分け合うことになるユスティニアヌス将軍の親衛隊員だった。しかしローマ軍によって二度目の侵攻がアルメニアへとなされた時、ナルセスとアラティウスが予期せずして彼らに立ち塞がり、会戦でこれを破った。この者たちは遠からぬうちに脱走兵としてローマ人のもとへとやって来て、ベリサリウスと共にイタリア遠征を行った。しかし目下のところ彼らはシッタスとベリサリウスの軍と戦って彼らに対して優位に立った。またトラキアのリベリウスが指揮を執るもう一つのローマ軍によって遠征が行われ、ニシビス市近くまで攻め込んだ。何の苦難にも遭わなかったにもかかわらずこの軍は不意に逃げだし、退却した。このために皇帝はリベリウスを職から解いてベリサリウスをダラスにいる部隊の司令官に任命した。この歴史書を書いたプロコピウスが彼の相談役に選ばれたのはこの時のことであった。 この後、ユスティニアヌス帝はベリサリウスを東方担当司令官に任命し、対ペルシア人の遠征を行わせた。彼は実に恐るべき軍勢を集めてダラスへと向かった。マギステル職を帯びたヘルモゲネスもまた申し分なく軍を動かすのを支援するために皇帝のもとから彼のもとへと向かった。この人は以前にウィタリアヌスがアナスタシウス帝と戦争をした時にはウィタリアヌスの相談役だった人物だった。皇帝は自分の指示があるまでユーフラテス川のヒエラポリスに留まるよう命じた上で大使としてルフィヌスも送ってきた。というのも和平について双方ですでに多くのことが述べられていたからだ。しかし、ペルシア軍がダラス市を占領しようと望んでローマ人の土地に侵攻すると予測されるという報告が突如としてベリサリウスとヘルモゲネスのもとに入ってきた。これを聞くと彼らは以下のようにして戦いの準備をした〔530年7月。〕。ニシビス市の反対側にある門からそう遠くなく、石が投げ捨てられていたところに彼らは多くの通路を持った深い壕を、そこを横断する形で掘った。この壕は真っ直ぐに掘られておらず、以下のような具合になっていた。その真ん中にはやや短い直線区画があり、これの両端に最初の壕に対して直角に交差する二つの壕が掘られた。彼らは二つの交差する壕の端から始めて元々の方向へ向けて二つの真っ直ぐな壕をかなりの距離を掘り続けた。そう遠くないうちにペルシア軍が大軍でやって来て、その全軍はダラス市から二〇スタディオン離れたアンモディオスと呼ばれる土地に陣を張った。この軍の指揮官の中にはピテュアクセスと隻眼のバレスマナスがいた。しかし全軍を統括していたのは「ミラネス」(ペルシア人はこの職をこう呼んでいた)という称号を持ったペロゼスという名のペルシア人の将軍だった。このペロゼスはベリサリウスに風呂の準備をしておけという手紙をすぐに送ってきた。それというのも彼は翌日にそこで入浴しようと見込んでいたからだ。したがってローマ軍は次の日の戦いを予期して会戦のためにこの上なく精力的に準備を行った。 日が昇って敵が前進してくるのを見ると、彼らは以下のように布陣した。交差する壕と繋がっていた左側の真っ直ぐな濠の端からその近くにあった丘に至るまでの部署は騎兵の大部隊を率いるブゼスと三〇〇人の同胞を率いるエルリ人のファラスが占めた。彼らの右側で、壕の外側、交差する壕とその地点から延びる真っ直ぐの区画によって角度ができていた箇所は生まれがマッサゲタイ人〔フン族〕のスニカスとアイガンが六〇〇騎の騎兵を連れて陣取っており、それはブゼスとファラスの部隊が撃退された時に側面へと素早く移動することで敵の背後を取り、その地点のローマ軍を支援しやすくするためであった。他方の翼にもマッサゲタイ人は同じような具合で配置された。真っ直ぐな壕の端はニケタスの息子ヨハネス、キュリルスとマルケルスに率いられた騎兵の大部隊が占め、ゲルマヌスとドロテウスも彼らにつけられた。他方で右の端にはシマスとマッサゲタイ人アスカン率いる六〇〇騎の騎兵が陣取り、それはすでに述べたようにヨハネスの部隊が撃退されることがあれば彼らがそこから出撃してペルシア軍の背後を攻撃するためであった。このように壕に沿って全軍の歩兵と騎兵の部隊が陣取った。彼らの背後の中央にはベリサリウスとヘルモゲネスの部隊が陣取った。このように整列したローマ軍は二五〇〇〇人を数えた。しかしペルシア軍は歩騎四〇〇〇〇人から成り、彼らは全員で正面に向けて密集して陣取り、ファランクスの正面をできる限り分厚くした。それから長らく双方共に戦端を切らないままだったが、ペルシア軍はローマ軍の見事な陣立てに驚いてこのような状況ではどうしたものか途方に暮れていたようであった。 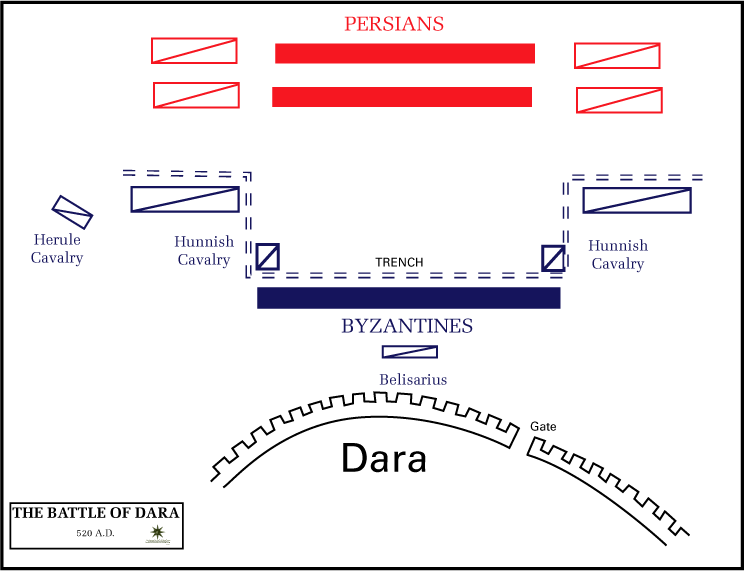 翌日にミラネスは夜明け頃に全ペルシア軍に呼びかけ、こう語った。「ペルシア人が危機に対しては勇敢でいることに慣れているのは彼らの指導者たちの言葉のおかげではなく、彼ら個々の勇気と互いに対する廉恥心のおかげだということを私は知らないわけではない。だが今までローマ人は混乱して取り乱すことなく戦いに向かうことに慣れていないにもかかわらず、決して彼らの性分ではないような秩序を守りつつ、進軍するペルシア軍を最近になって待ち構えているのは一体全体どういう理由なのかと諸君が考えているのを見るに、このために私は諸君のために激励の言葉をかけ、諸君がそれによって間違った意見を持つような理由によって騙されることがないようにしようと決めたのだ。というのも私としては、ローマ人が突然優れた戦士になって一層の勇気と経験を手に入れたとも、彼らが以前よりも一層臆病になったとも諸君に考えないでほしいからだ。いずれにせよ彼らはペルシア人を恐れており、それは彼らが壕なしにファランクスを組もうとはしないほどだ。これをしてもなお彼らは戦いを始めようとはせず、我々が彼らに戦いを仕掛ければ、彼らは喜々として、そして事の次第が彼らの期待以上に良くなっていると思いつつ城壁へと退却するという始末だ。またこれらの理由のゆえに彼らは混乱へと陥っていないだけであり、それもそのはず彼らは戦いの危険を未だかつて冒していないからだ。しかし戦いが間近に迫れば臆病風に吹かれ、そしてまったくの未経験のために、彼らは十中八九お決まりの混乱状態に陥ることだろう。かくして敵の境遇とはこのような具合である。だがペルシアの男たちよ、諸君は諸王の王の聖断をゆめ忘れることのないようにせよ。というのも諸君が目下の戦いでペルシア人の武勇にとって然るべき仕方で勇者の役を果たさなければ、不名誉な罰が下されるはずだ」この激励をしてミラネスは軍を敵に向けて率いていった。同様にベリサリウスとヘルモゲネスは防御設備の前に全ローマ軍を集め、以下のような言葉で激励した。「先の戦いで見計らったようにペルシア人が完全無敵ではなければ殺されることがないほどに強くもないことを諸君はしっかり分かっているはずだ。そして勇気と身体の強さにおいて完全に優っているにもかかわらず諸君はただむしろ指揮官の浅はかさのために敗れてきたことを誰も否定できまい。諸君は今このことの正しさを難なく了解できる機会を持つことになる。というのも運の逆境は決して努力によって直ることはない一方で、自らが種を蒔いた病に対して理性は容易く人間の医者になるからだ。したがってもし諸君が与えられた命令に聞く耳を持つならば、すぐに戦いで優位に立つことができるだろう。というのも我々に向かってくるペルシア人が頼みとしていることは我々の混乱を措いて他にないからだ。しかしまた今回も彼らはこの希望に落胆し、以前の戦いでそうしていたように退くことになるだろう。敵の数の多さについては、相手を怖がらせる以外のことではどうということはないので諸君は彼らを軽蔑するのが正しい。彼らの歩兵の全軍といえば、壁の向こうで穴を掘って戦死者から物を剥ぐためだけに、概して言えば兵士の手助けをするために戦場にやって来た取るに足らない百姓風情に過ぎない。こういうわけだから彼らは敵の難儀になるような武器を全く持っておらず、敵から打撃を受けないようにただ大盾を前に構えているに過ぎない。したがって諸君がこの一戦で自らが勇者であると示すならば、目の前のペルシア人に勝てるだけではなく、彼らの愚劣さを罰することにもなり、ひいては彼らはもう二度とローマ領に攻め込むことはなくなるだろう」 ベリサリウスとヘルモゲネスがこの激励を終えるとペルシア軍が前進してくるのが見えたため、彼らは急いで兵たちを前と同じように整列させた。彼らの前に向かってくると夷狄はローマ軍の前に立ちはだかった。しかしミラネスはペルシア軍の全軍ではなくその半分だけを敵に向けて整列させ、もう半分の部隊を背後に残した。彼らは戦闘中の兵と交代して無傷で元気なまま敵を攻めるために後置されており、このために交代で全軍が戦えるようになった。しかし彼はいわゆる不死隊の分遣隊にだけには自分が合図を出すまで休んでいるよう命じた。そして彼は前衛の中央に陣取り、ピテュアクセスに右翼の指揮を、バレスマナスに左翼の指揮を任せた。両軍は以上のように布陣した。ファラスがベリサリウスとヘルモゲネスの前に来てこう言った。「エルリ隊共々わしがここにいては敵に大きな損害を与えられるとは思えません。だが我らがこの斜面に隠れ、ペルシア軍が戦いを始めた時にこの丘を駆け上って彼らの背後に突然現れて後ろから射撃すれば、十中八九最大限の損害を与えることができましょうぞ」彼がこう言うとベリサリウスと彼の幕僚はこれを喜んだため、彼はこの計画を実行に移した。 しかし昼頃まではいずれの側も戦いの火蓋を切らなかった。しかし正午を過ぎるやすぐに夷狄が戦いを開始したのであるが、それは彼らが習慣的に午後にしか食事を取らない一方で、ローマ人は正午前に食事を取るという理由でこの時まで戦いを遅らせていたからだった。このために彼らは空腹の相手に攻撃をかければローマ軍はそう持ち堪えられないだろうと踏んでいた。そこでまず双方は矢の応酬をし、大量の矢玉が放たれたことでいわば大きな雲がかかったようになった。そして双方で多くの兵が倒れたが、夷狄の矢玉はより濃密によどみなく出てきた。常に新手の兵が交代で戦うことで敵が事の次第を把握するための僅かな好機すら掴めないようにした。しかしたとえそうだとしてもローマ軍の戦況は最悪というわけではなかった。というのもいつも起こる追い風が夷狄へと吹きかけ、彼らの矢の威力を相当に減殺したからだ。次いで双方が矢玉を使い果たした後、彼らは互いに槍を使い始め、戦いは白兵戦に移行した。ローマ軍の左翼がとりわけ苦戦した。というのもピテュアクセスと共にその地点で戦っていたカディセノイ人部隊が突如大挙して襲いかかって敵を敗走させ、逃亡兵を激しく追い込んでその多くを殺したからだ。これが部下によってスニカスとアイガンの知るところとなると、彼らは大急ぎで彼らに向けて突撃した。しかし最初にファラス指揮下のエルリ人部隊三〇〇人が高台から敵の背後に出て敵全て、特にカディセノイ人部隊に対して見事な勇気を発揮した。ペルシア軍はスニカスの部隊もすでに側面からこちらに向かいつつあることを知ると、引き返して急いで遁走した。敗走は全面的なものとなったが、それというのもここでローマ軍は互いに部隊を合流させて夷狄への大殺戮が起こったからだ。この機動によってペルシア軍の右翼では三〇〇〇人を下らない死者が出た一方で、残った者は苦労しつつファランクスの方へと逃げ込んで助かった。ローマ軍は追撃を続けず、両軍は列をなしつつ互いに対峙した。出来事の経過は以上のようなものであった。 しかしミラネスは密かに左翼へと大部隊を送っており、それにはいわゆる不死隊の総員が添えられていた。これらに気付いたベリサリウスとヘルモゲネスはスニカスとアイガン麾下の六〇〇人の兵に右翼の角へと向かうよう命じ、そこはシマスとアスカンの部隊が陣取っていて、彼らの後方にベリサリウスの手勢の多くが配置されていた部署だった。こうしてバレスマナス指揮下で左翼に陣取っていたペルシア軍は不死隊と一緒に向かい側のローマ軍に突進し、ローマ軍はその攻撃を支えきれずに早々退却した。そこでその角にいたローマ軍と彼らの後方にいた全軍は追撃者に向けて激しい熱意をもって前進した。しかし彼らがその方面から夷狄の方へと向かったおかげで敵軍を二つに分断し、より大きい方が右翼になった一方で、後方に残された部隊が左翼を占めることになった。その中にバレスマナスの旗持ちがたまたまおり、スニカスは彼めがけて突進して槍で襲いかかった。追撃を先導していたペルシア軍はすでに自分たちの苦境に気付いており、反転して追撃を切り上げて敵の方へと向かったが、このために敵に左右両側を晒すことになった。というのも彼らの前で敗走していた者たちは何が起こったのかを知って再び回れ右したからだ。ペルシア軍の不死隊の分遣隊と共にいた隊はというと、軍旗が傾いて地面に下ろされたのを見てバレスマナスのところにいたローマ軍にこぞって突っ込んでいった。そこのローマ軍は踏ん張って持ち堪えた。この結果、夷狄は大いに恐怖して最早抗戦を考えられなくなり、総崩れになって逃げ出した。ローマ軍は輪を作るように彼らを取り囲んでおよそ五〇〇〇人を殺した。したがってペルシア軍は退却し、ローマ軍は追撃をするという具合で両軍全体が動き出した。戦場のこの場所ではペルシア軍にいた全ての歩兵が盾を投げ出し、敵に捕捉されて片っ端から殺された。しかしローマ軍は追撃をそう遠くまでは続けなかった。というのもペルシア軍が必要に迫られて逆襲に転じ、無鉄砲に追撃をしているローマ軍を敗走させることを恐れたベリサリウスとヘルモゲネスが彼らにそれ以上進むことを全く許さなかったからで、彼らは無傷の勝利を守ることで満足していたようだった。その日にペルシア軍は会戦でローマ軍に負かされたわけであるが、そのような出来事は長年起こったためしがなかった。こうして両軍は互いに分かれた。ペルシア人は最早ローマ軍と会戦を行おうとはしなくなった。しかし何度かの突発的な襲撃が両陣営の間で交わされたが、その中でローマ軍が劣勢になることはなかった。メソポタミアの軍勢の命運は以上のようなものであった。 これからそう遠からぬうちにメルメロエスは全軍を集結させてローマ領へと攻め込み、サタラ市近くにいた敵のもとへとやって来た。そこで彼らはその都市から五六スタディオン離れたオクタウァと呼ばれる土地で陣を張って休止した。したがってシッタスは彼らの背後にあってサタラ市がある平地を囲むたくさんの丘のうちの一つに一〇〇〇人の兵を連れて隠れた。彼は残りの軍を連れていたドロテウスに防備線の内側に留まるよう命じたが、それは敵兵力が三〇〇〇〇人を下らなかった一方で自軍は敵の半分ほどもいなかったために平地では全く敵に歯が立たないだろうと考えたからだ。翌日に夷狄は防備線の近くまで来て易々と町に近づいた。しかしそこで高台から駆け下りてきたシッタスの部隊を見た彼らは、夏期だったおかげで土煙が舞ったためにその数に皆目見当がつかなかったため、敵が自軍よりも遙かに大勢だと思い、町の近くの平地を慌ただしく放棄してより狭い地形に軍を大急ぎで集めた。しかしローマ軍はその動きを予想して兵力を二隊に分けていたのであり、彼ら〔シッタスの別動隊〕は防御線から退く敵に襲い掛かった。そしてこれを見ると全ローマ軍は勇を鼓し勢い良く防御線から飛び出して敵に向けて進んだ。したがって彼らはペルシア軍を挟み撃ちにして敗走せしめた。しかしすでに述べたように夷狄は敵に対して数で非常に優っていたためになおも抗戦を続け、狭い場所での激戦となった。双方は全部が騎兵だったために敵に前進して攻めかかってはすぐに退却するという戦いを繰り広げた。そこで騎兵部隊を率いていたトラキア人フロレンティウスが敵の中央に突撃をかけて将軍の旗印を奪い、それを地面に打ち倒して後退し始めた。彼自身は追いつかれ倒され滅多打ちにされたものの、彼は自らをローマ軍に勝利の主因だと証明した。旗印がもう見つからなくなると夷狄は大混乱して恐慌状態に陥り、退却して野営地の内側に向かい、戦いで多くの兵を失ったために大人しくした。翌日に彼らは追跡を受けることなく全軍で帰国したが、それはローマ軍にとってはこれほどの夷狄の大軍勢に対して自国領で先ほど述べたように被害を与えるのは大仕事であり、敵地に攻め込んだ暁には手ぶらで帰るかより数の少ない軍に敗れるかすることになるだろうと思われたからだ。 その時にローマ軍はペルサルメニアにあるボロン砦とファランギオン砦と呼ばれるペルシア方の砦についても知り、後者はペルシア人が金を採掘して王に渡していた場所にあるものだった。また、たまたまこれから少し前に彼らはツァニ族を服属せしめており、このツァニ族は昔から自治権を持った民としてローマ領に住んでいた。それらのことがどのようになされたのかを今ここで述べてみたい。 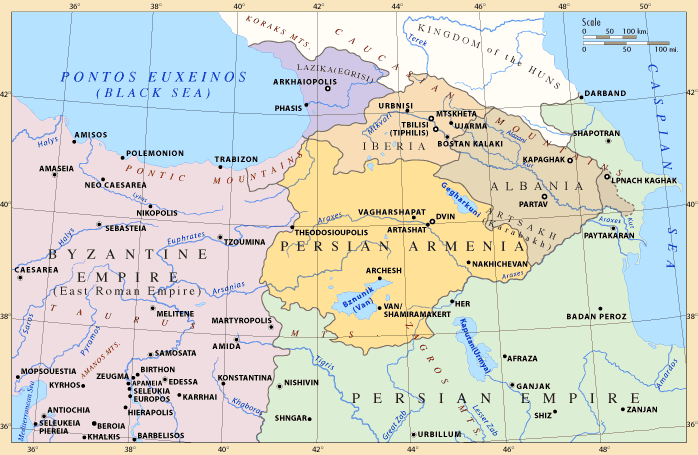 この人々の境界の向こうには城壁は高く著しく急な渓谷があり、それはコーカサス山脈まで広がっている。そこには人口の多い町々があり、ブドウとその他の果物が豊富に生っている。三日分の旅程の広さのこの渓谷はローマに年貢を払っているが、そこからペルサルメニア領が始まっている。ここには金山があり、カバデスの許可の下でシュメオンという一人の現地人が働いていた。このシュメオンは両民族が活発に戦争をしているのを見て取ると、カバデスから収入を奪ってやろうと決めた。したがって彼は自分とファランギオンの両方をローマ人に差し出したが、鉱山の金を差し出すのは拒んだ。敵がそこからの収入を奪われるだけで十分に思ったローマ人としては何もせず、ペルシア人はローマ人の意に反しその地の住民に条件を出すことができなかったが、それはペルシア人がその扱いにくい地域に手こずっていたからだった。 時を同じくして、上述のようにこの戦争の劈頭にペルサルメニア人の土地でシッタスとベリサリウスと対戦したナルセスとアラティウスが母を連れてローマ人のもとへと脱走してきた。皇帝の家令のナルセスは彼らを受け入れ(それは彼もまたペルサルメニア人の生まれだったからだ)、彼は彼らに多額の金を贈った。このことが彼らの末弟イサキオスの知るところとなると、彼はローマ人と秘密交渉を行ってテオドシオポリスの境界のすぐ近くにあったボロン砦を彼らに引き渡した。彼は〔ローマ軍の〕兵士たちに付近のどこかに隠れるよう指示し、小さい門の一つを密かに空けて夜のうちに彼らを砦へと引き入れた。こうしてまた彼もまたビュザンティオンについた。  オレステスが姉妹を連れてタウロス人のもとから急いで出発した時、たまたま彼は病を得た。彼がその病について調べたところ、彼の厄介事はタウロス人のいる場所にアルテミスのために神殿〔と都市〕を建設し、彼の髪を切って髪にちなんだ名前を都市につけるまで和らぐことはないという神託の応答を受けた。かくしてオレステスはその地方を廻ってポントスまで来て、険しくそびえ立つ山の端の下に沿ってイリス川が流れているのを見つけた。したがってオレステスはその時にここが神託によって示された場所だと思い、そこに大きな都市とアルテミスの神殿を建設して自分の髪を切り、それにちなんで都市を名付け、今日に至るまでそこはコマナと呼ばれている。この話は、これらのことを行った後にもオレステスは以前通り、いや輪をかけて激しく病に苦しみ続けたという風に展開する。それからその男はこの行いが神託に当てはまらなかったのだと気付き、再び方々を見て回り、カッパドキアのある場所にタウロス人のもとの都市と非常に似た都市を建設した。私自身はしばしばこの地を眺めて頗る賞賛してきたものであり、自分がタウロス人の土地にいるのを想像したことだってある。というのもタウロス山脈はここにもあってサロス川〔今日のセイハン川。タウロス山脈から発して南西向きにキリキアを流れ、地中海に流れ込む。〕はあちらにあるユーフラテス川に似ているため、こちらの山は他方の山ととても似ているからだ。かくしてオレステスはそこに堂々たる都市と二つの神殿を、一つはアルテミスのために、他方は彼の姉妹のイピゲネイアのために建設し、キリスト教徒はこれらの建物に全く手を入れることなく自分たちの聖域にした。ここはオレステスの髪にちなんで今日でもなお「黄金のコマナ」と呼ばれており、彼はそこで髪を切って苦しみから逃れたと言われている。しかし彼が逃れたこの病は自らの母を殺した後の彼に降りかかった狂気以外の何でもないと言っている人たちもいる。しかし私としては元の話に戻ることにしたい。 ユーフラテス川はタウロスのアルメニアとケレセネの土地から発してティグリス川の右側を流れつつ広大な土地の周りを回って流れており、豊かな水流はいわゆるペルサルメニア人の土地から流れ出ているアルシヌス川を含めた多くの川が合流しているためにユーフラテス川は自然に大河になり、昔には白シリア人〔レウコシュロイ人〕と呼ばれるが、今は小アルメニア人として知られている人々の土地へと流れ、彼らの第一の都市メリテネは非常に重要な都市である。そこからその川はサモサタとヒエラポリスとアッシリア地方に至るまでのその地方の全ての都市を通過し、アッシリア地方で二つの川〔ティグリス川とユーフラテス川〕は互いに一つの川へと合流し、ティグリス川という名前〔今日の呼び名はシャットゥルアラブ川。〕になる。サモサタから始まりユーフラテス川の外側〔タウロス山脈の水源からシリアのバルバリッソスあたりまでユーフラテス川はおおむね南北に流れており、ここでの「外側」とはこの西岸を指すものと思われる。〕に横たわるその土地は昔はコンマゲネと、今日はその川にちなんだ名前〔エウフラテシア〕で呼ばれている。しかし川の内側、つまりその川とティグリス川の間は正確にはメソポタミアという名である。しかしその一部はこの名前だけでなく、他の名前でも呼ばれている。アミダ市までの土地はある人たちからはアルメニアと呼ばれている一方で、エデッサとその周辺の地方は以前その地方がペルシア人と同盟を結んでいた時にその土地の王だったオスロエスにちなんでオスロエネと呼ばれている。したがってその後、ローマ人からニシビス市並びに他のメソポタミア諸都市を奪うとペルシア人はいつでもローマ人に対する遠征を行えるようにし、その大部分が水のない人が捨てた土地だったユーフラテス川の外側の土地は無視してここに難なく集合した。彼らは自分たちの領地と、敵の人の住む土地に非常に近い土地に住んでおり、ここから常々攻め込んだ。 戦いで敗れて大部分の兵を失い、残余の軍を連れてペルシア領に戻ると、ミラネスはカバデス王の手で重罰を受けた。カバデスは彼からいつも頭髪をとめていた金と真珠の細工を施された髪飾りを取り上げた。当時これはペルシア人の間では非常に大きな権威あるもので、栄誉では王に次いでいた。というのも王によって相応しいとみなされた者以外が金の指輪や帯や頭飾りや他のこの類いのものを身につけるのは法律で許されていなかったからだ。 その後、カバデスはローマ人に対する親征をどのようにしようかと考え始めた。というのもミラネスが上記のやり方で失敗した後に彼は他の人を信用できなくなったからだ。彼がどうしたものか完全に途方に暮れていると、サラセン人の王アラムンダラスが彼の面前に来てこう言った。「おお陛下、何であれ運命に委ねてはなりませんし、全ての戦争が成功するなどと信じるべきでもありません。それといいますのも、こんなことは適当なことではございませんし、人間の出来事の成り行きを踏まえておりませんが、このような考えに取りつかれる人たちにとってはこのような考えは最も不幸なものです。万事がうまくいくことを期待する人たちはある時にたまたま失敗した時、彼らをまずく導いた希望そのもののせいで然るべき以上に落ち込んでしまうものです。したがって好運を必ずしも常に信用しなければ、安直に戦争の危険に飛び込むことはなく、あらゆる面で敵を上回っていると自信を持っていたとしても、偽計と様々な計略によって敵を出し抜くことに関して熟練することになります。互角の勝負で危険を冒す者が勝利を確信することはございませんから。さて、そこでです、諸王の王よ、ミラネスに降りかかった不運に思い悩んではなりませんし、運命を試そうなどと望んではなりません。メソポタミアといわゆるオスロエネの地は陛下の国境のすぐ近くにあるため、それらの諸都市は他の全ての都市よりも非常に堅固であり、今のこれらにはかつてないほど多くの兵がいるので、もし我々がそこに向かえば、戦いの安全は不透明なことでしょう。しかしユーフラテス川の外側の土地とそれと隣接するシリアの土地には要塞化された都市もなければ重要な軍勢もいません。このことについて私は間諜としてそちらの地方へと送ったサラセン人どもからしばしば聞き知っております。彼らが言うには、富と大きさと人口では東のローマ帝国第一の都市であるアンティオキア市も無防備で兵がいないという話です。というのもこの都市の人々は祝祭と贅沢暮らし、、そして劇場での競い合い以外のことしか頭にないという始末です。したがって我々が彼らに不意打ちをかければ、その奇襲攻撃でその都市を落とし、メソポタミアの部隊が事の次第を知るより先にペルシア人の都市へと敵軍と会うことなく戻れるであろうこと必定です。水や食料の欠乏に関して陛下が考えるに及びません。なんとならば私自身が最善と思われる所へと軍を率いて行くからです」 カバデスはこれを聞くとその計画に反対せず疑いもしなかった。というのもアラムンダラスは最も分別がある古強者であり、徹頭徹尾ペルシア人に誠実で、類い希な活発さを持った人物で、五〇年もの間ローマ人の国を屈服させ続けていた人物だったからだ。彼はエジプトの境界から始めてメソポタミアあたりまでの全域を略奪し、ある土地から他の土地へと次々と略奪を働きつつ進路上の建物は焼き払い、襲撃のたびに何万人もの人を捕虜にしてその大部分は容赦なく殺した一方で、他の者は多額の金と引き換えに解放した。彼の前に立ち塞がる者は全くいなかった。というのも彼は下調べをせずには決して攻め込まず、好機を見計らって出し抜けに動き出していたため、概して将兵が事の次第を知って彼に向けて集結し始めていた時にはすでに彼は全ての略奪品を持ち去っていた。現にたまたま彼らが彼を捕捉できたとしても、この夷狄は追撃者がまだ戦闘隊形を組めず準備もできていないところに襲いかかって難なく敗走させて壊滅させたことだろう。そしてある折には彼を追撃していた部隊を指揮官たち共々全員捕虜にしたこともあった。この指揮官はルフィヌスの兄弟ティモストラトス、ルカスの息子ヨハネスで、中々の、あるいは平凡な財産を得たことで彼は後者を後に釈放した。つまるところ、この男は自らが全ての敵の中で最も手強く危険な敵であることをローマ人に見せつけたのだ。これができたのはアラムンダラスが王の地位を保持してペルシアの全サラセン人を一人で支配し、常に全軍を連れてローマ領の望む所ならばどこであれ攻め込めることができたからだった。そしてローマ人が「ドゥクス」と呼ぶローマ軍の指揮官、「ヒュラルコス」と呼ばれているローマ人と同盟していたサラセン人の指導者の誰一人としてアラムンダラスに兵を率いて太刀打ちできなかった。というのも別々に配置されていた部隊では敵と戦っても歯が立たなかったからだ。このためにユスティニアヌス帝はガバラスの息子でアラビアのサラセン人を支配していたアレタスにできるだけ多くの氏族の指揮権を与えて彼に王の称号を授けたわけであるが、このようなことをローマ人はかつてしたことがなかった。しかしアラムンダラスは少なくとも以前並にローマ人に被害を与え続け、それはアレタスがどの作戦と戦いでもきわめて不運であったか、そうでなければ彼が早々に裏切り者になったせいだった。というのも彼について確実なことは我々には何も分からないからだ。このようにしてアラムンダラスは何ら抵抗を受けずに東方全土を非常に長い期間略奪したものであるが、それは彼が非常に長命だったからだった。 したがってペルシア軍はカリニクス市のちょうど向かい側のユーフラテス川岸に野営した。そこから彼らは全く人の住まない地方を通って進軍することでローマ人の土地から離れようとした。というのも彼らには最早以前のような具合で進もうという意図はなく、川岸に留まっていた。ローマ軍は夜にスラ市を通過してそこを離れ、ちょうど出発の準備中だった敵のもとにやって来た。この時は復活祭間近で、復活祭はその翌日だった〔531年4月19日。〕。この祝祭をキリスト教徒は他のどの祝祭よりも大事にしており、前日には日中だけでなく夜の大部分の時間も飲食を謹んで断食するの習慣があった。したがってこの時ベリサリウスは全ての兵が敵に向かおうというやる気に満ちているのを見て取ると、この考えを捨てるよう彼らを説得しようと望んだ(というのもこの方針は、最近皇帝からの使節任務で来ていたヘルモゲネスから勧められたことでもあった)。したがって彼はその場にいた全員に呼びかけ、こう話した。「おおローマ人諸君、諸君はどこへ急いでいるのだ? 諸君は徒に危険を選ぶつもりでいるが、それは一体どういうわけなのだ? 人々は完全無欠の、つまり敵の手で何の被害も受けないような勝利がただ一つだけあると信じているわけだが、これはまさに目下の事例での好運、そして我々の敵を打ちひしぐ恐怖によって我々に与えられたものだ。したがって恩恵がもうなくなった時にこれを求めるよりは我々の手元にある恩恵の利益を享受する方が良かろう。というのもペルシア人は多くの希望に突き動かされてローマ人に対する遠征を行ったが、今は全てを失って大急ぎで撤退する羽目になっているのだから。だからもし我々が撤退という彼らの目的を彼らの意志に反して放棄させて我々との戦いを強いたならば、我々が勝利しても我々には何の益もなく――なぜ逃げる者を追い散らすべきだというのか?――他方でもし我々に運がなければ、ことによると我々は今手にしている勝利を奪われ、その勝利を敵に盗み取られるのではなく自ら放り出し、皇帝陛下の土地を今後守る者もいないまま敵の攻撃に明け渡すことになってしまう。さらに神は自分から危機を選ぶ者ではなく必要があって危機に陥っている者を常に助けるものであることも諸君が考えるに値することだ。これとは別に進退谷まった者は自らの意に反してでも勇者としての役割を果たすことになる一方で、戦いに突入するにあたって我々に立ち塞がる諸々の障害は数多くある。諸君の大部分は徒歩で、我々全員が断食状態だ。今なお味方の一部が到着していないということを述べるのを私としてはやめておく」ベリサリウスはこのように述べた。 しかし軍は沈黙のうちにではなく、憚ることなく彼を軽蔑し始め、彼の面前にがなりたてに来ては彼を弱虫、自分たちの熱意の破壊者と呼んだ。一部の将官たちでさえ兵士と一緒になってこの侮辱を行うことで自らの勇気の程を示そうとした。彼らの破廉恥ぶりに仰天したベリサリウスは自分の奨励する策を転換し、自分は彼らの戦意を以前は知らなかったが今は自分も見事な勇気を持っており、より希望を持って敵に立ち向かうつもりだと話し、今や彼らを敵に差し向けるよう駆り立てられて彼らを戦いへと向かわせることにしたようだった。そこで彼はファランクスを一列に並べ、兵を以下のように配置した。川が近い左翼に歩兵の全部隊を配置した一方で、地面が激しく隆起している右翼にはアレタスと彼のサラセン兵の全部隊を置いた。ベリサリウス自身は騎兵と共に中央に陣取った。ローマ軍の布陣は以上のようなものだった。そしてアザレテスは敵が戦闘隊形に集まっているのを見て取ると、以下のように兵たちを激励した。「ペルシア人諸君、諸君らが命と引き換えに勇気を捨て去るつもりはないことを否定できる者はいない。だがたとえ諸君らが望まずとも、諸君には二つのものから一つを選択する力があると私は言いたい。危機と不名誉な生から逃げる機を持つ者たちであれば、望むならば最善のものの代わりに最も心地よいものを選ぶであろうということは全くもって不自然なことではない。だが、敵の手で栄光ある死を迎えるか諸君の主君による罰へと恥知らずにもいざなわれるかの運命にある者ならば、最も恥ずべきことの代わりにより良いことを選ばないというのはきわめて愚かしいことである。さて、したがって物事がこのようになるならば、敵のみならず主君のことを覚えつつこの戦いに向かうのが諸君皆に相応しいことだと私は考えるものである」 また、このような激励の言葉を述べた後にアザレテスはファランクスを敵に向けて配置し、ペルシア兵を右翼に、サラセン兵を左翼に配した。間もなく両軍は戦いに入り、戦いは激しいものとなった。双方から放たれた夥しい数の矢が両軍に多くの犠牲者を出した一方で、ある者たちは両軍の間に出てきては互いに向けて勇気を示し、とりわけペルシア軍では多くの者が矢で倒れた。というのもペルシア軍はほぼ全員が射手で他の誰よりも遙かに素早く射撃を行う術を学んでいたためにペルシア軍の矢は比べようのないほどの頻度だったが、もかかわらず矢を放った弓は弱くピンと張ることができなかったので彼らの矢はローマ兵の胴鎧に、あるいはことによると兜や盾に命中すると砕けてしまい、命中した兵士に怪我を負わせるだけの威力がなかった。ローマの射手はいつも後れを取っていたが、彼らの弓はきわめて堅く非常に張りが良く、加えてこれらを扱っているのは剛力の兵であり、いかなる鎧も彼らの弓の威力を防ぐことができなかったため命中すればペルシア兵以上により多くの者を容易く殺すことができた。一日の三分の二が過ぎた時にも戦況は未だ互角だった。そこで〔ペルシア人〕相互の合意の上でペルシア軍の中の最良の全部隊がアレタスとサラセン兵の陣取るローマ軍右翼に攻撃をかけた。しかし彼らは戦列を崩して去ったため、彼らはローマ軍をペルシア軍に売り渡したという悪評を被った。それというのも彼らは敵が近づいてくるのを待たずにすぐさま大急ぎで退却したからだ。したがってペルシア軍はこのようにして敵の戦列を突破してすぐにローマ軍騎兵部隊の背後に回り込んだ。かくしてすでに進軍と戦い両方での疲労で疲弊していた――これに加えてその日は何も食べていなかった――ローマ軍は今や前後両側からの敵の攻撃を受けることとなり、最早持ち堪えられず総崩れになった彼らの大部分は近くにあったいくつかの川中島へと向かった一方で、踏み止まった一部の者は敵に対して驚くべき目覚ましい戦いぶりを示した。その中にはアスカンもおり、彼は多くのペルシア人貴族を討ち取った後にじわじわと滅多打ちにされ、敵に彼を記憶する理由をたっぷりと残しつつついに倒れた。彼と一緒に他の八〇〇人がこの戦いで自らが勇者であることを示しつつ死に、イサウリア兵のほぼ全部は武器を敵に対して掲げることさえせずに指揮官もろとも死んだ。それというのも彼らはつい最近農業をやめてその時まで未知だった戦争の危機へと入ってきたばかりで、この仕事の経験が全くなかったからだ。さらにその兵たちは直前には戦争への無知のために戦いに関する全ての事柄に最も激怒し、ベリサリウスを臆病だと非難していた。実際のところ、彼らは全員がイサウリア人というわけではなく、大部分がリュカオニア人だった。 少数の兵と共にここに留まっていたベリサリウスはアスカンと彼の兵たちが踏み止まっているのを見て、彼もまた手元にいた部隊を率いて敵を食い止めた。しかしアスカンの部隊の一部が倒されて他の者たちが逃げられる限りのところへと逃げ出すと、ついに彼も兵を連れて逃げ、その大部分が逃げてしまったおかげで今はもう数が多くはなかったもののペトルスがまだ戦っていた歩兵のファランクスの方へと向かった。そこでベリサリウスは自ら馬を捨て、配下の兵全員も自分に倣うよう命じ、迫り来る敵を他の兵と共に徒歩で退けた。逃げる者を追っていたペルシア兵は短い距離だけ追撃した後、すぐに方向を点じて歩兵と他の全部隊を伴っていたベリサリウスに襲いかかった。この時、ローマ軍は川を背にしていたために敵は彼らを包囲する機動を取れず、ローマ軍は状況が許す限り敵の攻撃に対して防戦した。再び戦いが激化したが、両軍の戦力は互角というわけではなかった。というのもほんの一握りの歩兵がペルシアの全騎兵部隊を相手にしていたからだ。にもかかわらず敵は彼らを敗走させることもできず、どうにもこうにも圧倒することもできなかった。肩と肩を組んだ彼らは常に狭い場所にひとまとまりになって踏みとどまり続け、盾をしっかり構えて堅固な障害を築いたため、彼らはペルシア軍に撃たれる以上に彼らを都合良く射撃することができた。幾度となく諦めた後にもペルシア軍は彼らの戦列を突破して破壊しようという決意を持って彼らに向けて前進していたことだろうが、彼らの攻撃はいつも不首尾に終わり、すごすごと引き下がる羽目になった。というのも彼らの馬は盾とぶつかり、腹を立てたために後馬は後ろ足で立ち上がり、自らと騎手に混乱をもたらした。このようにして双方はその日に遅くなるまでまで戦い続けた。夜がすでに迫っていた時にペルシア軍は野営地へと退き、僅かな兵を連れていたベリサリウスは輸送船を見つけて川中島へと渡り、その一方で他のローマ兵は泳いで同地にたどり着いた。翌日、多くの輸送船がカリニクス市からローマ軍のもとへと届けられて彼らはその船団で対岸まで届けられ、ペルシア軍は死者から持ち物を剥いだ後に全軍が帰国の途に就いた。しかし彼らは敵に劣らぬ死者が自軍でも出ていたことに気付いていなかった。 アザレテスが軍と共にペルシアに到着した時、彼は戦いで勝利していたにもかかわらず以下のような理由でカバデスから全く感謝されなかった。ペルシア人には以下のような風習があった。彼らが敵に差し向けられる時、玉座に座った王の前にたくさんの籠が置かれる。そして軍を敵に差し向けることが予想されている将軍も出席する。それから軍が王の面前を通過し、一度に一人ずつ各々がその籠に武器を投げ入れていく。この後にこれらの籠は王の印章で封をされて保管される。この軍がペルシアへと戻る段になると、各々の兵は籠から武器を取り出した。兵士に取り出されなかった武器全部が担当者たちによって数え上げられ、彼らは帰ってこなかった兵の数を王に報告することになっていたわけであるが、このようにして戦争でどれだけの死者が出たのかが明らかになる。このような法が昔からペルシア人にあった。さてアザレテスが王の面前へとやってくると、アラムンダラスと一緒にアンティオキア制圧を目指してローマ人に向けて出撃していたアザレテスに対してカバデスはどれかローマの砦を奪って帰ってきたかと問いかけた。一つも砦を落とさなかったが、ローマ軍とベリサリウスを会戦で破ったとアザレテスは述べた。そこでカバデスはアザレテスの軍に例の通過をさせ、習わし通り各々の兵は籠から武器を取り出した。しかし多くの武器が残ったためにカバデスはアザレテスを勝利の件で叱責し、その後に最も信用ならない人物の一人としてみなすようになった。アザレテスにとってのこの勝利の結末は以上のようなものだった。 パレスティナの境界のすぐ向こう側のこの沿岸〔アラビアの沿岸を指す(N)。〕はサラセン人が占拠しており、彼らは「椰子の木立」に昔から住んでいた。この木立は内陸部にあってかなりの土地に広がっており、椰子の木以外はそこでは何も生育しない。ユスティニアヌス帝はこの椰子の木立をそこのサラセン人支配者のアボコラボスから贈り物として受け取り、彼は皇帝によってパレスティナのサラセン人の部族長に任命された。彼は絶えざる略奪からその土地を守っていたわけであるが、それは支配下の夷狄並びに敵の両方に対してアボコラボスは常に恐るべき男で、際だって精力的な人物だったからだ。したがって皇帝は形式的には椰子の木立を保有しつつも、正味のところその土地の一部を手に入れることさえまったくできなかった。それというのも一〇日分の旅程の距離だけ広がっていたその土地は人間の居住に必要な物を完全に欠いていて極めて乾燥しており、さらに椰子の木立自体は何ら値打ちのあるものではなく、アボコラボスは形式的な贈り物としてそこを差し出しただけで、皇帝はその事実を百も承知でそこを受け取っていた。椰子の木立についてはこのくらいにしておこう。この人々に隣接し、沿岸を領するマッデノイ人と呼ばれている他のサラセン人がおり、彼らはホメリタイ人〔アラビア半島南東部を支配していたヒムヤル王国。〕に従属している。ホメリタイ人は沿岸部側の父祖伝来の土地に住んでいる。彼らの向こう側には人食いサラセン人のいるところに至るまで多くの民族が住んでいると言われている。その向こう側にはインドの諸部族がいる。しかしこれらの事柄を検討するにあたっては望ましいところで述べることにしたい。 ホメリタイ人の対岸の土地にはアウクソミス市に王が座しているためにアウクソミタイ人と呼ばれるエティオピア人〔アウクソミスはエチオピア北部の都市アクスムのこと。この都市を中心としてエチオピアを支配したアクスム王国。〕が住んでいる。その間に広がる海は順風に恵まれれば昼夜五日間で渡ることができる。その海域には全く浅瀬がないので、彼らはここから夜に航行するのにも慣れていた。この海域は一部の人たちからは「紅海」と呼ばれている。アラビア人の王が早い時期にペトライ市〔アイラスの北方にある。〕に宮殿を置いていたおかげでここ〔アイラス〕からガザ市の境界まで広がる地方は昔アラビアと呼び習わされていたため、この地点から先、アイラス市と岸まで横切る海は、アラビア湾という名をつけられていた。今はエティオピアへの航海のためにホメリタイ人が海へと漕ぎ出すのに馴染んでいる港はブリカスと呼ばれており、海への航海が終わると彼はいつもアドゥリス人〔エチオピア沿岸の都市。〕の港に停泊する。しかしアドゥリス市は港から二〇スタディオン離れており(だからそこは海にあるものだけがなかった)、アウクソミス市からは一二日分の旅程のところにあった。 インドとこの海域で見られる全ての小舟は他の船と同じような具合に作られてはいない。それらは瀝青も他の物質も塗られておらず、鉄鋲でとめられた板もついておらず、紐で縛ってとめられていただけだった。この理由は、大部分の人が考えるようにそこには鉄を自分に引きつけるある岩があった(そんなことはかつてなかったが、ローマの船がアイラスからこの海に航行した時にその岩に多くの鉄を引きつけたという事実の証言がある)からではなく、むしろインド人もエティオピア人も鉄なりこの手の目的に適した他の資材を持っていなかったからだ。さらに法律で全ての人に明確に禁止されていたために彼らはローマ人から何かそういった物を買うことすらできなかった。その法に触れた者には死刑に処されている。いわゆる紅海〔むしろ「アラビア湾」である(N)。〕とその両側にある土地の記述はこれくらいにしておこう。 アウクソミス市からローマ領エジプトの境界までのところにエレファンティネと呼ばれる都市があり、荷物を持たない旅人なら三〇日の旅程のところである。その地には多くの民族が住んでおり、そのうちブレミュエス族とノバタイ族は非常な大民族である。しかしブレミュエス族はその地方の中心部に住んでいる一方で、ノバタイ族はナイル川あたりを領有している。ローマ帝国の境界は以前はここではなく、これより向こう側、七日の旅程分進んだあたりまでだった。しかしローマ皇帝ディオクレティアヌスがそこに来て、それらの地からの貢納が最小限の量で、その土地はこの時点では非常に狭く(ナイル川からほど遠からぬところで非常に高く隆起している岩がその地方の残りを覆っていたからだ)、その一方で大部隊が昔からそこに配置されており、そこの維持は公衆にとって甚だしい重荷になっていたのを見て取った。同時に、以前にはオアシスの都市に住んでいたノバタイ族がその地方全域で略奪を働いていたため、彼は大きな諸都市と彼らが前にいた所とは比べものにならないほど良い広大な土地を授けることをこの夷狄に約束し、彼らを彼らの居住地を去ってナイル川沿いに移住するよう説き伏せた。それというのも、こうすることで彼らは少なくともオアシス近辺の土地を襲撃しなくなるだろうし、彼らは与えられた土地を自分たちの土地として保持してブレミュエス族と残りの夷狄たちを追い払ってくれるだろうと彼は考えたからだ。これはノバタイ族を喜ばせたため、彼らはディオクレティアヌスが指示した通りにすぐに移住し、全てのローマ都市とエレファンティネ市より向こう側のナイル川の両岸の土地を手に入れた。それからこの皇帝は、ローマ人の都市をもう略奪すべきでないと取り決めて彼らとブレミュエス族に毎年所定の額の黄金を渡すと布告を発した。彼らは私の時代に至るまでこの黄金を受領しているものの、その地方を襲い続けていた。したがって全ての夷狄には彼らを見張る部隊への恐怖以外、ローマ人への誠意を守るよう強制するものは何もなかったように見える。さらにこの皇帝はエレファンティネ市に近いナイル川のとある川中島を選び、非常に堅固な砦を建設してその中にローマ人とこれらの夷狄共用の神殿と祭壇を建て、神聖なものを共有すれば友好が確かなものとなるだろうと考えてこの砦に両民族の祭司を配置した。このために彼はその地をフィラエと名付けた。ブレミュエス族とノバタイ族の両民族は今もギリシア人が信仰する全ての神々を信仰しており、また彼らはイシスとオシリスも崇敬しているが、とりわけプリアプスを崇敬している。しかしブレミュエス族は太陽に人間を生け贄に捧げるという慣習も持っている。フィラエの聖域は私の時代でもなおこれらの夷狄によって保持されていたが、ユスティニアヌス帝はそこを取り壊そうと決意した。したがって生まれがペルサルメニア人で、私が前に述べたようにローマ人のもとへと脱走してきたナルセスが部隊の指揮官となり、皇帝の命令でその聖域を取り壊し、司祭を監視下に置いてビュザンティオンに〔神々の〕像を送った。ここで元の話に戻ることにしたい。 この輩はそう遠からぬうちにある他の人たちと一緒にエシミファイオス王に対して蜂起して砦の一つに彼を幽閉し、ホメリタイ人にアブラモスという名の他の王を立てた。さてアブラモスはキリスト教徒だったが、エティオピアのアドゥリス市で船積みの仕事をしていたローマ市民が使っていた奴隷だった。これを知ると、ヘレステアイオスはエシミファイオスへの不正行為のためにアブラモスを彼と一緒に反旗を翻した者たち共々罰してやりたいと思い、彼らに彼の親族の一人を司令官とした三〇〇〇人の軍を送った。そこに来るとこの軍は帰国の意志を失ってその良い土地に留まることを望んだため、彼らの司令官の知らぬところでアブラムスとの交渉を開始した。それから彼らがまるで戦い始めるかのように敵との戦闘に向かうと、司令官を殺して敵軍と合流し、そこに留まった。しかしヘレステアイオスは激怒して彼らにもう一つの軍を差し向けた。この軍はアブラモスと彼の兵と戦い、会戦で大損害を被った後にすぐに帰国した。その後、エティオピア人の王は不安に駆られ、アブラモスに向けてさらなる遠征軍を送った。ヘレステアイオスの死後、アブラモスは彼の跡を継いだエティオピア人の王に貢納を払うことに合意することで支配権を強化した。しかしこれは後に起こる話である。 ヘレステアイオスがエティオピア人の上に、エシミファイオスがホメリタイ人の上に君臨していたこの時、ユスティニアヌス帝は両民族が同じ教えを奉じる誼から対ペルシア戦争でローマ人に味方してくれるよう求めるためにユリアヌスを使者として送った。それというのも彼は、インドから絹を買ってローマ人に売っているエティオピア人が大金を手に入れていていた一方でローマ人がたった一つの道で利益を得られることを、つまり彼らが最早敵〔ペルシア人〕に金を払わなくて良くなることを目指していたからだ。(これは昔のギリシア人がメディケと呼び、今日は「セリケ」と呼ばれる服を作るのに彼らが使っている絹である〔これはラテン語のsericaで、中国(Seres)に由来する」(N)。〕。)ホメリタイ族は避難民のカイソスをマッデノイ人の族長にし、彼ら自身の民の大軍とマッデノイ系サラセン人と併せてペルシア人の土地に攻め込もうと望んだ。このカイソスは族長階級の生まれの極めて優秀な戦士だったが、エシミファイオスの近親の一人を殺しており、人間の居住に全く向かない土地へと避難していた。かくしてそれぞれの王はこの要求の実行を約束して使節を帰したが、彼らのうち一人たりとも合意した通りに動かなかった。というのもペルシア人商人がインド船が最初に泊まる港に常駐していて(彼らは近隣の地方に住んでいたからだ)いつも積み荷を買い占めていたため、エティオピア人はインド人から絹を買うことができなかったからだ。そしてホメリタイ人には荒れ果てどこまでも続くその地方を長い時間をかけて渡り、自分たちよりも遙かに好戦的な民に向けて進むというのは難事だと思われていた。後にアブラムスもようやく権力をこの上なく確固たるものとした時、ペルシアの土地に攻め込むとユスティニアヌス帝と何度も約束したが、たった一回向かってすぐに引き返すという有様だった。ローマ人がエティオピア人とホメリタイ人と結んだ関係とは以上のようなものであった。 昔からローマ人とペルシア人の間では大枚をはたいて間諜を保有するのが慣行となっていた。何が起こっているのかを精確に調査するために彼らは密かに敵のもとへと潜り込み、帰国して支配者たちに報告するというのが常だった。当然ながら彼らの多くは国への忠誠心を持って働いていた一方で、一部の者は裏切って敵に機密を漏らしてもいた。当時、ペルシア人からローマ人のもとへと送られていたある間諜がユスティニアヌス帝の面前に来て夷狄の間で起こった多くの事柄を、とりわけマッサゲタイ族がローマ人に危害を加えるために、ペルシアの土地に赴いてペルシア軍と合体してローマ人の領土に攻め込む用意をしていることを暴露した。これを聞くと、この男が真実を語っているという証拠をすでに持っていた皇帝は彼に気前良く大金を与えて以下のようにするよう説き伏せた。マルテュロポリス人を包囲しているペルシア軍へと赴き、そこにいる夷狄にローマ皇帝が金を使ってマッサゲタイ族を味方につけ、まさに彼らが彼らに来襲しようとしていると知らせよ、と。この間諜はこれらの指示を実行に移し、夷狄の軍のもとに来るとカナランゲスと他の人たちに対し、彼らに敵対するフン族の軍勢がローマ人のために間もなくやってくるぞと知らせた。これを聞くと彼らは恐慌状態に陥り、目下の情勢にどう対処したものか途方に暮れてしまった。 この時期にカバデスが重病で臥せ、彼はメボデスという名の側近のペルシア人を自分のもとに呼び寄せてホスローと王国について相談し、ペルシア人が自分の諸々の決定を無視して重大な企図を実行に移すのではないかと恐れていると話した。しかしメボデスは彼に自らの意図することを文書の形ではっきり残すよう求め、こうすればペルシア人は決してこれを無視できないだろうと信じさせた。こうしてカバデスはホスローがペルシア人の王となるべしと明確に定めた。メボデスその人が書き上げたその文書をカバデスはすぐに人々に広めた。王の埋葬時に万事が法で定めた通りに行われると、カオセスは法のおかげで自信を持ちつつ政権を〔自分が執ると〕主張しようとしたが、メボデスは何人たりとも自分勝手に王権を振るうべきではなく、ペルシア人貴族たちの議決に基づくべきだと主張して彼に異を唱えた。かくしてカオセスは法廷では自分に対する異論が出ることはなかろうと考え、問題を法廷に委ねることを決めた。しかし全てのペルシア人貴族がこの目的のために集められて話し合っていた時、メボデスがこの文書を読み上げ、ホスローについてのカバデスの目論見を述べ、カバデスの威徳を思い起こした皆はすぐにホスローをペルシア人の王であると宣言した。 このようにしてホスローは権力を確立した。しかしマルテュロポリスでは、危機からそこを防衛することが到底できなかったシッタスとヘルモゲネスはこの都市について心配しており、彼らは敵方に人を遣って将軍たちを前に以下のように話させた。「貴下らは自らがペルシア人の王と和平の承認と両国に対する悪しき障害となりつつあることをご存じでないようです。といいますのも、皇帝陛下から送られた使節団は、ペルシア人の王のもとに赴いて厄介事を解決し、協定を樹立するために今なおここにおります。してみれば貴下らはできるだけ速やかにローマ人の土地を離れ、使節団が両国の人々のためになるような仕方で行動できるようにしていただきたい。我々にはこれらが実際にそう遠からぬうちに解決するであろうことを示すため、目下の事案においては令名高い人たちを人質として差し出す用意がございます」ローマ人の使節団の言葉は以上のようなものであった。宮殿からの伝令も彼らのもとにやって来て、カバデスが死んでカバデスの息子ホスローがペルシア人の王になり、このような具合で状況が不安定になったという言伝を彼らのもとに持ってきた。この結果、フン族の攻撃をも恐れていた将軍たちはローマ人の言葉に喜んで耳を傾けるようになった。したがってローマ人はすぐにマルティヌスと、シッタスの親衛隊の一員で名をセネキウスという人を人質として渡し、ペルシア人は包囲を解いて速やかに立ち去った。そう遠からぬうちにフン族がローマ人の土地に攻め込んできたが、ペルシア軍が見つからなかったので襲撃を早めに切り上げて全軍で帰郷した。 しかし一方でペルシアには嘘の報告が届き、これによればユスティニアヌス帝は激怒してルフィヌスを処刑したというものだった。現にホスローはこれに大層動揺したが、それまでにすでに腹を立てていたので全軍を率いてローマ人の方に攻め込んだ。しかし帰路のルフィヌスは途上の彼とニシビス市からそう遠くないところで会った。したがって彼らはこの都市に赴いて和平を締結しようとしたため、使節団はそちらに金を運び始めた。しかしユスティニアヌス帝はラジカの諸々の砦を諦めたことをすでに後悔していたため、使節団に決してこれらをペルシア人に渡してはならないと明確に指示する手紙を書き送った。このためにホスローはもう協定を結ぶのは適当だとはみなさなくなった。それからペルシアの土地に金を運ぶにあたって安全よりも速さを優先して協議を行ってしまったとルフィヌスは思い至った。したがってすぐに彼は地面に身を投げ出し、金を送り返してローマ人に向けてそうそうすぐに軍を進めずに他の時まで戦争を延期して欲しいとホスローにひれ伏しながら懇願した。ホスローは彼を地面から立たせ、これら全てのことを認めると約束した。こうして使節団は金を携えてダラスへと来て、ペルシア軍は引き返した。 それからルフィヌスの同僚使節たちは彼を極度に疑うようになり、ルフィヌスの求めの一切に関して同意するようにホスローが説得されたという事実についての彼らの判断に基づき、皇帝に向けて彼を謗った。しかし皇帝はこのために彼を疎んじることはなかった。そう遠からぬうち、続けざまにこのルフィヌスその人とヘルモゲネスが再びホスローの宮廷へと送られ、彼らは協定に関して互いにすぐに合意に達した。その条件とは、双方は戦争で他方から切り取った全ての土地を返還してダラスを今後は軍事基地としないというもので、イベリア人に関する決定〔12章を参照。〕については、ビュザンティオンに留まるか祖国に戻るかについては彼ら次第とすることで合意した。多くの人が留まったが、父祖の土地へと帰った者もまた多かった。こうして彼らはいわゆる「恒久和平」を締結し、これはユスティニアヌス帝の治世六年目のことであった〔532年。〕。ローマ人はペルシア人にファランギオンとボロンの砦を金と一緒に譲り、ペルシア人はローマ人にラジカの諸要塞を譲った。またペルシア人はダガリスをローマ人に返し、彼と引き換えに立派な身分の他の人を受け取った。後にこのダガリスは、ローマ人の土地に攻め込んできたフン族をしばしば戦いで破って撃退したほど極めて有能な軍人だった。かくして上述のように双方は協定を確かなものとした。 しかしザメスの息子カバデスは殺せなかった。というのも彼はまだカナランゲスのアデルグドゥンバデスの養育下にいたからだ。しかし彼はカナランゲスに手紙を送り、養育していた少年を殺すよう指示した。というのも彼は不信感を示すのは得策と考えていなかったし、ましてや彼に強制する権能を持っていたわけでもなかったからだ。こうしてホスローの命を聞いたカナランゲスは不運を非常に嘆き悲しみ、妻とカバデスの乳母に王の命令の一切合切を伝えた。そこでこの女たちは涙を流し夫の膝を掴みながらカバデスを断じて殺さないよう懇願した。したがって彼らは相談し、この子を極秘に育ててホスローにはカバデスはこの世を去ったという旨の手紙を急いで出そうと計画した。彼らは王にこの結論の手紙を送り、事の次第が誰にも発覚しないようにカバデスを隠したが、彼らの子供のヴァラメスと、あらゆる点で最も信頼が置ける一人の家来はその例外だった。しかし時が経ってカバデスが成人に達すると、カナランゲスはこの件が明るみに出るのではないかと恐れ始めた。したがって彼はカバデスに金を与えて出立させ、どこへなり逃げて我が身を守るようにさせた。その時、ホスローと他の全ての人たちはカナランゲスがこのことをやりおおせたという事実を知らなかった。 以下で述べるように、後にホスローは大軍を率いてコルキス領に攻め込んだ〔「第2巻17章を参照」(N)。〕。この同じカナランゲスの息子ヴァラメスが多くの家来を率いて彼のもとにはせ参じ、この中にはカバデスの身に起こった多くの事柄に関わっていた者もいた。他方でヴァラメスはそこでカバデスについての一切合切を王に話し、彼はその家来を連れてきて、この家来は一切合切について彼に賛同した。これを知るとホスローは激怒し、これを自分の奴隷の手から受けた忌々しい所業だと考えた。そしてこの男を自らの手中に収めるためなら手段を選ばず、以下のような計画を練った。コルキス領から帰国しようとしていた時、ユーフラテス川の両岸から敵に攻めかかるために一つの道だけを使わずに全ペルシア軍を二分割してローマ領に攻め込むことを決意したという手紙をホスローはこのカナランゲスに書いた。さて軍のうち一軍は当然ながらホスロー自身が敵地へと率い、その一方で彼は武勇の故に見込んだカナランゲス以外どの臣下にもこの件で王と同等の栄誉を担う特権を認めなかった。したがって王がカナランゲスと相談して軍の動かし方についての一切の指示を与えるようにするため、カナランゲスは王が帰還すると急いで出迎えに向かって道中王にお供として付き従う必要があった。自らが窮地に立ったことをつゆ知らぬカナランゲスはこの言伝を受けると、王が示してくれた栄誉に大喜びし、すぐに命令を実行に移した。しかし旅の途中、旅の苦労にまったく耐えられずに(彼は非常に老齢だったからだ)手綱を持つ手が緩んで落馬し、足の骨を折った。したがってそこで大人しく治療を受ける必要が生じ、王はその地に来て彼を見舞った。こんな足の状態では遠征に同行するのはできないが、その地方のどこかの砦に行って医師の処置を受けるべきだとホスローは彼に言った。かくしてホスローはこの男を死へと続く道へと送り出し、砦で彼を滅ぼすために兵に跡を追わせた――事実この男はペルシア人の間では敵なしの将軍として名高く、一二の異民族に向けて軍を進めてこの全てをカバデス王に服属させていた。アデルグドゥンバデスが世を去った後、その息子ヴァラメスがカナランゲスの地位を受け取った。これからそう遠からぬうちにザメスの息子であるカバデスその人、あるいはカバデスを称する他の何者かがビュザンティオンにやってきた。なるほど彼はカバデス王に非常によく似ていた。彼に疑念を持ってはいたもののユスティニアヌス帝は非常に懇ろに彼を迎え入れてカバデスの孫としての栄誉を授けた。ホスローに対して蜂起したペルシア人はこのような仕儀になった。 後にホスローは以下のような理由でメボデスをも滅ぼした。王がある重要案件に関わっていた時、その場にいたザベルガネスにメボデスを呼ぶよう命じた。当時たまたまザベルガネスはメボデスと不仲だった。ザベルガネスがメボデスのもとに来た時、メボデスは自分の指揮下にある兵が整列する様の閲兵を行っており、ザベルガネスは王が可及的速やかに来るよう召したと述べた。目下の仕事が片付き次第すぐに跡を追うつもりだとメボデスは約束したが、彼への敵意に突き動かされたザベルガネスは、メボデスは何か仕事があると言い立てて参上を嫌がったとホスローに報告した。したがってホスローは怒りに突き動かされて従者の一人にメボデスを三脚台へと向かわせるよう命じて送り出した。ここでこれが何なのか私はすぐに説明すべきであろう。この鉄製の三脚台はいつも宮殿の前に立っているもので、王が自分に対して腹を立てているのを知ったペルシア人は聖域に逃げ込んだり他の場所に行ってはならず、この三脚台の近くに立って王からの沙汰を待たなければならず、何人たりとも彼を庇ってはならない。そこでメボデスはホスローの命で捕らえられて処刑されるまで何日も哀れな状態でそこに座り続けた。ホスローの善行の最終的な結果は以上のようなものだった。 しかしこの時、ビュザンティオンを管理する都の役人たちが一部の暴徒を刑場に引いていった。しかし二派の成員たちは共謀して互いに休戦を宣言し、〔刑場に連れて行かれる途中の〕囚人を奪ってそれからすぐに獄舎に押し入り、騒擾を起こしたとして有罪判決を受けていた者も他の違法行為を働いていた者もお構いなしに幽閉されていた者全員を解放した。市政の職に就いていた全ての属官たちは無差別に殺された。その一方、同じ事を考えていた全ての市民が対岸の本土へと逃げ、あたかも敵によって成されたかのように都で火の手が上がった。ソフィアの聖域とゼウクシッポスの浴場〔以下で出てくる施設の位置関係についてはこちらの地図が分かりやすい。〕、そしてプロピュライアからいわゆるアレス殿あたりまでの宮殿の区画、さらにアゴラまで続くコンスタンティヌスの名を冠した大柱廊、さらには金持ちらの多くの家屋、非常に多くの宝物庫までが炎で崩壊した。この間に皇帝とその妻は少数の元老院議員を伴って宮殿に引っ込んで事態を静観していた。今や人々が互いにニカ〔「勝利せよ」(N)。〕という標語を広め、この暴動は今日に至るまでこのような名で呼ばれている〔「ニカの乱」。〕。 時の近衛長官はカッパドキア人のヨハネスで、パンヒュリア生まれのトリブニアヌスが皇帝の顧問で、後者をローマ人は「財務官」と呼んでいる。二人のうち一方のヨハネスは初等学校に通っていた時は書き物のこと以外何にも関心がなく満足に勉強しておらず、また学ぶにしてもあまりにも貧乏だったため、文芸の教養が全く欠けていた。しかし天性の才能によって彼は我々が知るうちで最も有力な人物に成り上がった。というのも彼は必要なことを決断したり難事への解決策を見出す点において最も有能だったからだ。しかし彼は誰よりもさもしい人物になり、低俗な企みを推し進めるために生まれ持った力を行使した。神と人を前にした廉恥心への憚りも彼の心中にはなく、利得のために多くの人の人生を破壊して全ての諸都市を破滅させることが彼の変わらぬ関心事だった。現に彼は短い期間で莫大な金を手に入れ、浅ましい飲んだくれ生活にすっかり浸った。毎日昼時まで彼は臣民の財産を略奪し、その日の残りは飲酒と野放図な色事に浸りきった。彼は自制心を全く欠いており、吐くまで食べ物を食べ、金を盗むのが習いになっており、さらにこれに輪をかけて浪費癖があった。この時のヨハネスというのはこういう男だった。他方でトリブニアヌスは天性の才能と教育による学識を兼ね備えており、同僚の誰にも引けを取らなかった。しかしきわめて金に汚く、いつも喜々として利得のために正義を売り渡していた。したがって概して彼はいつもある法律を廃止しては他の法律をこしらえ、支持を頼む人たちに必要に応じて法律を売り渡していた。 事ここに至りて人々は色組の名のもとに互いにこの戦争を行うに至り、これらの人たち〔ヨハネスとトリブニアヌス〕を攻撃するためなら法への違反を一顧だにしなかった。しかしすでに述べたように、両派は互いを認識すると暴動を起こし、それからこの二人に責め苦を与えて殺すべく都中を公然と捜索した。したがって民衆を味方に付けようとして皇帝はすぐにこの二人を解任した。彼は最も思慮分別があって正義の守護者たるに相応しい人物だったパトリキウスのフォカスを近衛長官に任命し、パトリキウスのうちで愛想の良さで知られていて名士でもあったバシリデスに財務官職を勤めるよう命じた。しかし彼らの下でも暴動はなおも激しく続いた。さて、暴動五日目の午後、ユスティニアヌス帝はヒュパティウスとポンペイウスという先の皇帝アナスタシウスの二人の甥に可及的速やかに帰宅するよう命じた。これは自身に対する何らかの陰謀を彼らが仕込むのではないか、あるいは運命の力でこれ〔陰謀〕に彼らがいざなわれるかもしれないと皇帝が疑ったからだった。しかし人々が無理矢理に自分たちを戴冠させるのではないかと彼らは恐れ(事実その通りになった)、このような危機にある主君を捨てるとすれば、自分たちは悪事を働くことになってしまうと述べた。これを聞くとユスティニアヌス帝はいっそう疑念を掻き立てられ、即座に宮殿を退去するよう命じた。こうしてこの二人は自宅へと逃げ、夜の間はそこで大人しくした。 しかし翌日の夜明け時、この二人が滞在していた宮殿を立ち退いたことが人々の知るところとなった。こうして全ての民衆が彼らへと駆け寄り、彼らはヒュパティウスを皇帝と宣言し、権力を引き受けさせるためにアゴラへと彼を連れて行こうと支度した。しかしヒュパティウスの妻で思慮分別があり賢慮の点でこの上なく名高い女だったマリアは夫を掴んで行かせまいとし、人々が彼を死への道程へといざなっていると親族の全員に向かって大声で嘆き、懇願しつつ叫んだ。しかし群衆が彼女を参らせたために彼女は渋々夫を離し、彼はコンスタンティヌス広場へと嫌々ながら向かい、ここで彼らは彼を主君と呼んだ。彼らは冠も王が身につける習わしの他の物も持っていなかったので、頭に黄金の首飾りをかけてローマ人の皇帝と宣言した。この時までに元老院議員たちは――皇宮に残らなかった者に限り――集まっており、その多くは自分たちは戦うために宮殿へと向かうべきだという意見を披露した。しかし元老院議員の一人オリゲネスが来て以下のように述べた。「親愛なるローマ人諸君、我らの目下の状況を戦争以外によって解決することはできません。目下、戦争と帝権が世界のあらゆるもののうちで最大のものであるということは賛同されております。しかし行動が諸々の大きな問題を含む時、危機の瞬間に良い結論が得られることはなく、これは人々が長い間発揮してきた賢明な思考と精力的な行動によってのみ成し遂げられるものであります。それゆえ、我らが敵に立ち向かわなければならないとすれば、我らの大義は宙に浮いたどっちつかずの状態になり、我らは短時間のうちにあらゆることを決定するという危険を冒すことになります。こういった行為の結果として、我らは運命にひれ伏して祈りを捧げるか、運命を徹底的に難詰する羽目になるでしょう。それというのも概して運命の支配下でこういった問題が一番早く決するものですから。しかし我らが目下の状況をより慎重に取り扱うのであれば、たとえ我らが望んだところで宮殿にユスティニアヌスを連れてくることはできないでしょうし、彼に逃亡が許されたならば、彼はすぐにでも感謝することでしょう。というのも、無視された権威というものは日ごとに力が落ちるものなので、その力は常に失われるものだからです。さらに我らにはまだ他にも宮殿が、プラキリアナエ宮とヘレナにちなんだ名の宮殿が二つございますし、これを皇帝陛下は司令部にしてそこから戦争を行い、可能な限り最善の仕方で他の全てに関する命令を下すべく陣取るのがよろしゅうございましょう」オリゲネスが述べたのはこのようなことだった。しかし群衆にありがちなことだが、残りの人たちは今こそが好機だともっと興奮した様子で訴え且つ考えており、とりわけヒュパティウス(悪が彼に降りかかる運命にあったからだ)はヒッポドロームに向けて彼らを率いて向かった。しかし一部の人たちは、彼が皇帝になる気になっていたからそこへと意図的に来たと述べている。 今や皇帝と彼の廷臣たちは留まるべきか、それとも船で逃亡すべきかを協議するに至った。どの指針が望ましいのかについては多くの意見が披露された。テオドラも以下のような旨の話をした。「女は殿方に刃向かうべきでも、恐怖でたじろいでいる人たちの中で大胆な訴えをするべきでもないとわたくしは信じてはおりますが、目下の難局はああすべきかこうすべきかを検討する議論をわたくしたちに許さないほどのものだということはほぼ確実だと思われます。その利害が最大の危機に瀕している人ならば可能な限り最善の仕方ですぐに問題を解決するより外に最善の手はございません。わたくしの意見としては、たとえ身の安全を図るにしても、今逃げるのはまったく時宜を得ておりません。日の目を見た人が死を免れないように、皇帝になった人は逃亡になど耐られるものではありません。わたくしはこの紫衣を手放すつもりは毛頭ありませんし、出会う人から皇后様と呼びかけられないような日々を暮らしたくもありません。皇帝陛下、今あなたが自分の身の安全を望むならば、それは難しいことではありませんわ。わたくしたちはお金をいっぱい持っていますし、あちらには海があって、こちらには舟だってありますわ。でもね、あなたが助かった後、あなたは喜んで身の安全を死と取り替えるという仕儀になるのかどうか、考えてもご覧なさい。わたくしとしましては、帝位は素晴らしい死に装束であるという昔の諺に賛同するものです」皇后がこのように述べると、皆が大胆さに満たされ、彼らは抗戦へと考えをめぐらし、敵軍がやってくるとすればどうやれば自分たちの身を守れるのかと思案し始めた。この時、皇帝の宮廷に配置されていた部隊を含む兵たちは一丸となって皇帝側に立つ気はなかったが、かといって公然と刃向かって戦うつもりもなかったので、今後どうなるのか様子見していた。皇帝の全ての希望はベリサリウスとムンドゥスにかかっており、そのうち前者のベリサリウスは最近ペルシア戦争から帰ってきたばかりで、彼は力強く堂々とした従者団を従えており、とりわけ多数の槍兵と会戦と戦争の危険で鍛え上げられた親衛隊を持っていた。ムンドゥスはイリュリア人担当軍司令官に任命されており、夷狄のヘルリ人部隊を連れてある必要な用事でたまたまビュザンティオンに召喚されて来ていた。 ヒッポドロームに到着すると、ヒュパティウスはすぐに皇帝用の座席へと向かい、皇帝が競馬と陸上競技をいつも観戦している玉座に座った。宮殿から出撃したムンドゥスはそこの環状の下り坂から「かたつむり門」という名がつけられた門を抜けて進んだ。他方でまずベリサリウスはヒュパティウスその人と玉座へと一直線に進み始め、昔から親衛隊が詰めていた隣接する建物の方に来ると、自分が僭帝の方に行けるようにするためにできるだけ早く自分に扉を開けろと彼らに叫んで命令した。しかし兵士たちはどちらを支持すべきか決めかねていたので、そのうちの一方がはっきりと優勢になるまで何も聞こえないふりをして先延ばしにした。そこでベリサリウスは皇帝の方へと戻り、宮殿を守っている兵たちが謀反を起こしたから、もう自分たちの好機は失われたとはっきり述べた。したがって皇帝はいわゆる青銅門とそこにあるプロピュライアの方へと向かうよう指示した。こうしてベリサリウスは苦労しつつ廃墟と半焼けの建物で覆われた地面を進んで競技場へと上ったが、危険と大きな奮闘なしでは済まなかった。皇帝の玉座の右手にあった「青の柱廊」にたどり着くと、彼はまずヒュパティウスその人めがけて進んだが、そこにあった小さい扉は閉ざされ、内側はヒュパティウスの兵で守られていた。このため狭い場所で戦っている間に群衆が襲いかかってくるだろうと、そしてこうして自身とその手勢の全員は壊滅したならば彼らは難なく皇帝の方に来るだろうと彼は恐れた。したがってヒッポドロームに陣取っている――非常に大勢で相当にごった返していた――群衆の方に向かうべきだと結論づけると、彼は鞘から剣を抜いて他の者にもこれに倣うよう命じ、大声を上げながら彼らに向けて突き進んだ。しかし大勢で無秩序だった群衆は勇気と戦争経験で非常に名高い武装兵を眺め、彼らが情け容赦なく剣を振り下ろす様を見ると、慌ただしく退却しだした。それから当然ながら大きな抗議の声が生じ、そう遠からぬところにいたムンドゥス――これは果敢で精力的な男だった――は戦いに加わりたかったが、目下の状況では如何ともし難く途方に暮れていた。しかしベリサリウスが戦っている様を見ると、彼は「死の門」と呼ばれる入り口を通ってすぐにヒッポドロームへと突入した。それからヒュパティウス一派はこの死力を尽くした挟み撃ちに遭い、壊滅した。敗走が全面的なものになって大衆への大殺戮がすでに生じていた時、ユスティニアヌス帝の甥のボラエデスとユストゥスは誰からも手を挙げられることなくヒュパティウスを玉座から引きずり下ろし、彼をポンペイウス共々皇帝のもとへと連れて行った。この日の大衆の死者は三〇〇〇〇人以上にのぼった。かくして皇帝はこの二人の捕虜を厳しく軟禁するよう命じた。それからポンペイウスは涙を流して哀れを誘う言葉を吐き(この人はこのような悲運をまったく経験したことがなかったからだ)、ヒュパティウスは彼を長々と咎め、不正な仕方で死のうとする者が泣き言を言うなと述べた。最初、彼らは意に反して人々によって無理矢理に担ぎ上げられたが、後になって皇帝に危害を加えようという考えを持たずにヒッポドロームへと来た。翌日に兵士たちは彼ら二人を殺し、遺体を海に投じた。皇帝は彼らと彼らに味方した他の元老院議員全員の財産を没収して国庫に納めた。しかし後にヒュパティウスとポンペイウスの子供たち、他の全ての人たちに以前保有していた称号を返したが、彼らの財産に関してはユスティニアヌスが自分の友人たちに与えていなかった分だけを返還した。ビュザンティオンでの暴動の結末は以上のようなものだった。 テオドラ皇后は他の誰よりも彼を嫌っていた。悪事を働いてにこの婦人の怒りを招いても彼は何らかのお追従ないし親切によって彼女の心証を良くしようなとどは思わず、公然と彼女に敵対して皇帝に向けて彼女の讒言を続け、彼女の高い地位を前にしても顔を赤らめず、皇帝が彼女に抱いていた度を超した愛情によって恥じ入ることもなかった。事の次第を知ると、皇后はこの男を殺そうと企んだが、ユスティニアヌス帝が彼を重用していたのでどうやってもこれを果たせなかった。自分に関する皇后の狙いを知るとヨハネスはひどく怯えた。これ以前は〔近衛〕長官には保有が認められていなかった数千人の槍兵と護衛隊を引き連れていたにもかかわらず、毎夜寝室に寝に来る時には夷狄の何者かが自分を殺そうと襲撃してくるのではないかと備え、一睡もせずに部屋の外を除いて入り口を見張るというのを続けた。しかし夜明けには神的なものと人間に関わるものへの恐怖の一切を忘れ、彼は再び公私にわたってローマ人の厄介事になったようである。そして彼は妖術師らといつも語らい、彼に帝国での官職を予示する不敬な予言を絶えず聞いていたため、明らかに上機嫌になり、権力への希望で浮かれた。しかし彼の行いの非道と無法ぶりは穏健にならず、減ることもなかった。彼は神を一顧だにせず、祈祷をして夜を明かすために聖域に赴く時ですら、キリスト教徒がそのために行くようなことは何一つとして行わず、昔のキリスト教の司祭が着るようなきめの粗い、今はギリシア服と呼び慣わされる衣服を着て、いつも口にしているような不遜な言葉を夜通しつぶやきつつ、皇帝の心がいっそう自分の支配下にあり続けて自分が全ての人からの危害から解放されるよう祈った。 この時、イタリアを平定したベリサリウスが、ペルシア人に対して軍を進めるために妻のアントニナを伴いつつ夏にビュザンティオンにやって来た〔「6巻30章」(N)。〕。当然ながら彼が栄誉に満ちた卓越した人物だというのは衆目の一致するところであったが、ヨハネス一人が彼に対立して彼に対する悪巧みをしており、その理由は彼が全ての人から嫌われていた一方で人気においてベリサリウスの右に出る者がいなかったということ以上でも以下でもなかった。彼にしてみれば、ローマ人らの希望は彼が妻をビュザンティオンに残して今一度ペルシア人に向けて軍を進めることに存していた。ベリサリウスの妻アントニナ(彼女は不可能を可能にすることにかけては世界で最も有能な人物だった)は皇后に気に入られようとして以下のような計画を練った。ヨハネスにはエウフェミアという娘がおり、これが思慮分別で非常に有名だったが、非常に若い娘だったので影響されやすかった。この少女はたった一人の子供だったので父から溺愛されていた。この少女を何日も優しく扱うことでアントニナは完全に手懐け、この少女はアントニナに秘密を打ち明けるのを拒まないほどになった。ある折に部屋で二人きりでいた時にアントニナは自分に降りかかった運命を悲しむふりをした。彼女が言うには、ベリサリウスが立派な処置をすることでローマ帝国を以前よりも拡大させ、彼は二人の王を捕らえてビュザンティオンに莫大な富をもたらしたにもかかわらず、ユスティニアヌスには感謝の様子がないとベリサリウスは見ており、他のことについても彼女は政権は正義に悖ると悪口を言った。さて、皇后への恐怖から目下の首脳部に反感を持っていたエウフェミアはこういった話に狂喜し、こう言った。「それでもね、一番のお友達のあなた、機会があったのにあなたが自分の権力を用いようとしないのを見ますに、あなたとベリサリウス様はこの件について責任があります」アントニナはすぐさまこう返した。「私の愛娘、それは野営地で革命を起こすなどというのは私たちにはできないからなのですよ。私たちと組んでこの母国でこの事業に加わる人がいない限りはね。あなたのお父様にその気があれば、私たちがこの計画を準備して神の思し召すことは何であれするのは赤子の手をひねるようなものです」これを聞くと、その提案を実行に移すつもりだとエウフェミアは熱烈に約束し、父の前にその話を持ち込むべくすぐにその場を出て行った。この言伝を彼は喜び(この計画は彼の予言が成就して帝権を手に入れる一歩だと彼は推測したからだ)、躊躇せず即座に賛同し、翌日に彼自身がアントニナと会って誓約を交わすよう我が子に取り計らわせた。ヨハネスの腹を知るとアントニナは彼をできるだけ惑わして真相から遠ざけようとし、事の邪魔になるほどに疑われないようにするためには当面のところ自分と会うのは得策ではないと言った。しかし彼女はベリサリウスと合流するためにすぐ出発することになっていた。したがって彼女がビュザンティオンを去って郊外(ベリサリウスの私有地だったルフィニアナエと呼ばれる所)に到着した時、あたかも彼女に挨拶をして旅路を護送するためであるかのようにヨハネスはそこに来て、彼らは事の次第について相談し、誓約を交わすのが良い。こう言って彼女はヨハネスのためになる話をするかのように装い、計画の実行日を指定した。皇后はアントニナから一切合切を聞くと、彼女の計画に賛意を示し、よりいっそう奮起するよう激励した。 指定された日が間近に迫ると、アントニナは皇后に別れを告げて都を出発し、あたかも次の日に東方へと旅立つかのようにルフィニアナエに向かった。合意された計画を実行に移すためにヨハネスもこの夜にやってきた。その間皇后はヨハネスが独裁権力を確固たるものにしようとして行った諸々について夫に讒言し、ヨハネスが革命を進めているのが判明すればこの男を殺して直ちに帰還するようにと命じ、宦官ナルセスと親衛隊司令官マルケルスを多数の兵と一緒にルフィニアナエへと送った。こうしてこの任務のために彼らは出発した。しかし事の次第を皇帝は知っており、皇帝はアントニナと密かに会うのをどんなことがあろうともヨハネスに禁じるべくヨハネスの友人の一人を送ったと言われる。しかしヨハネスは(事をし損じるのが彼の運命だったからだ)皇帝の警告を無視し、ある壁のすぐ近くでアントニナと深夜に会った。その背後には話の内容を聞くべくナルセスとマルケルスが兵を連れて陣取っていた。そこでヨハネスが軽率に口を滑らし、攻撃の計画に賛同してこの上なく恐れ多い誓いでもって自らを縛ると、ナルセスとマルケルスは突如彼に襲いかかった。しかし当然の狼狽が起こった結果、ヨハネスの親衛隊(彼らはすぐ近くに待機していたからだ)が彼のもとへとすぐに駆けつけた。彼らの一人はマルケルスとは知らずに彼を剣で打ったのでヨハネスは彼らと共に逃げ果せることができ、大急ぎで首都にたどり着いた。すぐに皇帝の面前に赴くだけの勇気が彼にあったなら、彼は皇帝から何の危害も受けなかっただろうと私は信じている。しかしいわば彼は聖域に逃げ込むのを恐れ、自分を好きに処する機会を皇后に与えてしまった。 そしてこのようにして彼は長官から一市民になり、その聖域から、キュジコス市の郊外に位置してキュジコス人によってアルタケと呼ばれた他の聖域へと移された。そこで大変不本意ながらも彼は僧服を身につけたが、これはその呼び名通り司教用の長衣ではなく司祭用の長衣と呼ばれるものだった。しかしいつか〔元の〕職務に戻る邪魔にならないようにするため、彼には聖職者の職務を行う気が全くなかった。というのも彼は希望を捨てるつもりがさらさらなかったからだ。彼の全財産はすぐに没収されて国庫に納められたが、まだ彼を許す気が残っていたので皇帝はこの大部分を彼のために取っておいた。ヨハネスが好きなように贅沢に浪費し、そしてもし彼が賢明に考慮して目下の巡り合わせを幸福と考えていたならば、あらゆる危険を顧慮せずに莫大な富を享受しつつ、彼自身が隠して皇帝の決断で彼に残されたこの二つのもので暮らしていくことができた。このために全ローマ人はこの男に非常に苛立ったが、これは彼が自らが全ての悪人のうちで最も卑劣な者だと示した後に当然の報いに相反する形で以前よりも幸福な人生を送ったためである。しかし私の思うに、神はヨハネスへの報いをこれで終わらせたわけではなく、より大きな罰を彼のためにとっておいた。それは以下のような形で降りかかった。 キュジコスにはエウセビウスという名の司教がおり、これは自分の邪魔になる全ての人に対してはヨハネスにも劣らないほど情け容赦のない人物だった。キュジコスの人たちは皇帝に向けてこの人を誹り、法廷に召喚した。エウセビウスがその強権によって彼らの妨害を行ったので彼らは何らなすところがなく、ある若者たちが相謀ってキュジコスのアゴラで彼を殺した。折しもヨハネスは特にエウセビウスに敵意を持つようになっており、この陰謀への嫌疑が彼にかけられた。したがってこの汚らわしい行いを調査すべく元老院から人員が送られた。彼らは手始めにヨハネスを幽閉し、そしてかくも有力な長官で、パトリキウスたちの心に刻まれ、執政官の椅子に座ったこともあり、少なくともローマの国家ではこれほどの大物はいないと思われていたこの男を、強盗や追い剥ぎにするかのように裸で立たせ、背中に何度も強打を加え、過去の人生を話すよう強要した。ヨハネスがエウセビウス殺害の罪をはっきりと白状しないでいると、神の正義が世界中の罰を彼に科したかのような仕儀になった。その後彼らは彼の持ち物を全て取り上げ、数オボロスで買った生地の粗い外套一枚だけをかぶせて船の甲板で裸にした。船が投錨するところであればどこであれ、彼のことを任された人たちは会う人にパンか数オボロスの金を求めるよう彼に指図した。こんな風に道中物乞いをしながら彼はエジプトのアンティノウス市まで連れていかれた。そこに幽閉された彼を監視しているうちに今や三年目になった。ヨハネス自身はというと、このような難儀を被っていたにもかかわらず王権への希望を捨てておらず、あるアレクサンドリア人らを公金横領の廉で告発しようと腹に決めた。したがってその時にカッパドキア人ヨハネスはその政治経歴のために一〇年後にこのような罰に見舞われることとなった。 |